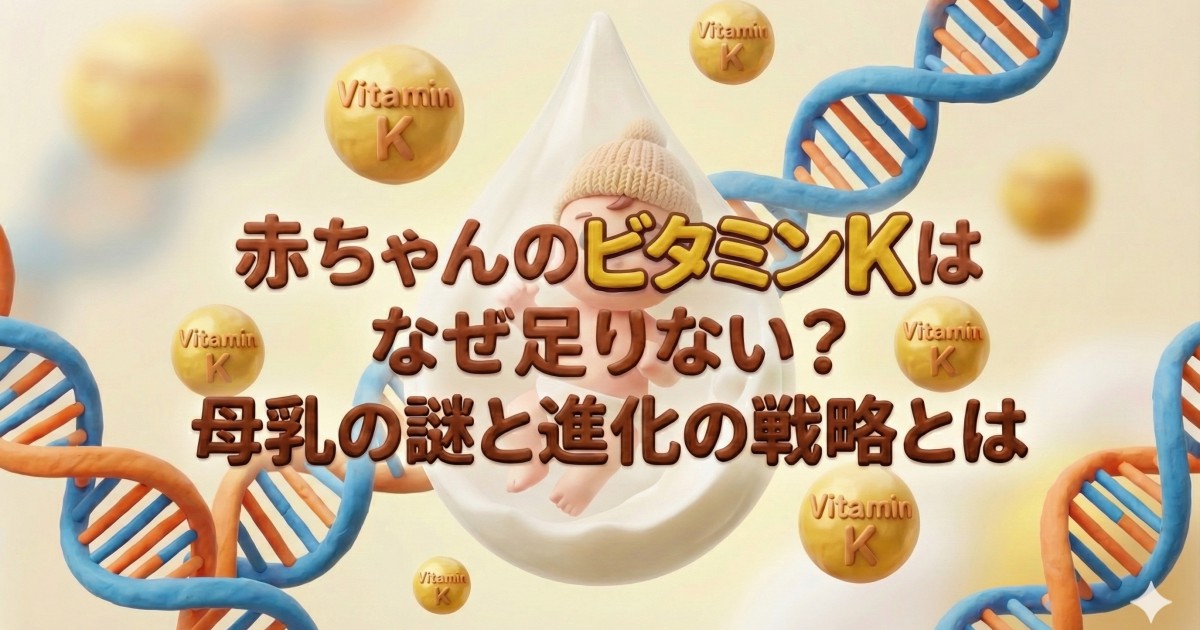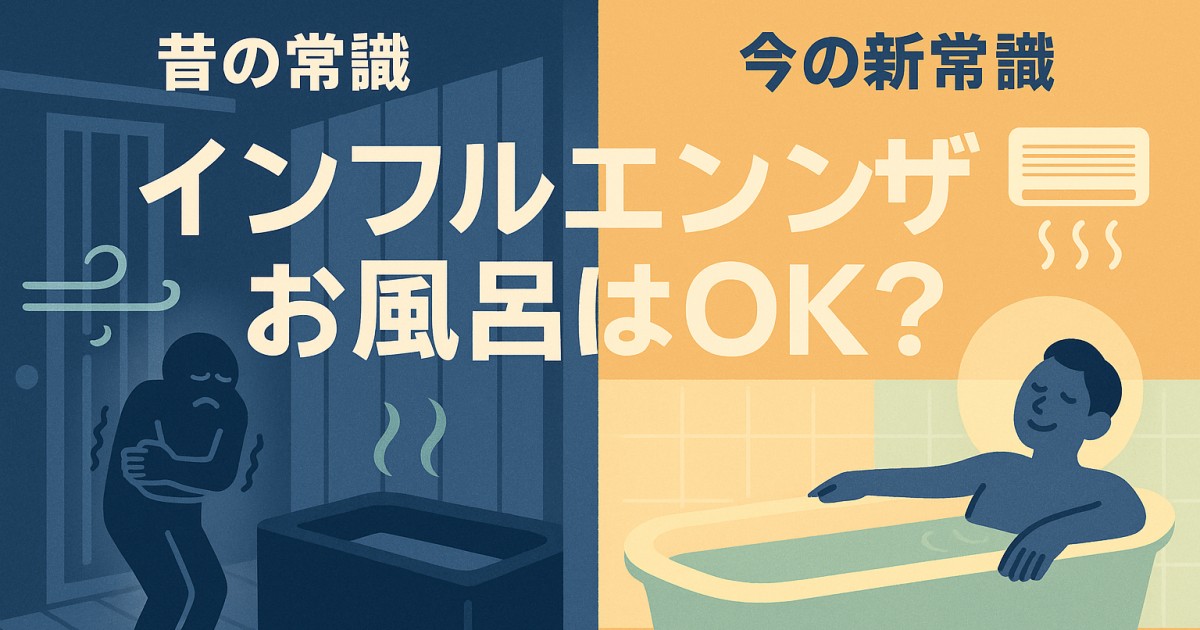マイコプラズマの薬『マクロライド系抗菌薬の苦み』に、どのように対策する?
しばらくなかった流行が、いよいよはじまったマイコプラズマ肺炎、さらに増加しています[1]。
そこで今回は、マクロライドというマイコプラズマに対する特効薬と言える、細菌を退治するための抗菌薬の一種に関して深堀りしていきましょう。
このニュースレターでは、さまざまな子どもやアレルギーに関する医療情報を豊富な出典に基づき配信しています。継続的に記事を受け取りたい方は、 メールアドレスを登録していただくことで 次回以降 メールで記事を お届けすることができます。よろしければご登録をよろしくお願いいたします。
マクロライドの作用メカニズム
マクロライドという名前は、『大きなラクトン環という構造を持っている』ことから名付けられました[2]。
すなわち、マクロは「大きな」という意味、ライドは「ラクトン環」という意味です。この2つの言葉を組み合わせてマクロライドという名前がついているのです。
マクロライドは、細菌の『リボソーム』というタンパク質を合成する装置に結合することで、細菌のタンパク質を作る力を邪魔して、細菌が増殖するのを抑える薬です[3]。
細菌が増えることができなくなると、やがて死滅してしまいます。つまり、マクロライド系抗菌薬は、菌の増殖を抑制する作用があるということになります。
マクロライド系抗菌薬と、よく聞く『ペニシリン』の違い

イラストAC
抗菌薬、つまり菌を殺す薬としては、ペニシリンという薬をよく聞いたことがあるのではないでしょうか。
ペニシリンは、βラクタム系という大きな括りの抗菌薬で、広く使われています。これらは細胞壁という細胞の周りの壁を合成するのを邪魔したり、壊したりする薬です。
しかし、細胞壁という壁をもともと持たない微生物に対しては、これらの薬は効果が極めて少ない、あるいは効かないということになります。
その細胞壁を持たない微生物の一つが、マイコプラズマなのです。
マクロライド系抗菌薬の歴史
マクロライド系抗菌薬の歴史は1952年に遡ります。
最初のマクロライド系抗菌薬であるエリスロマイシンは、フィリピンの土の中から発見されました[4]。これは自然に存在する物質だったのです。ある放線菌という菌が作り出す物質の中に、菌の増殖を阻害する活性を持つ物質として発見されました。
この記事は無料で続きを読めます
- マクロライド系抗菌薬の改良:きょうだいの様な『誘導体』
- マクロライド系抗菌薬の課題:苦みの問題
- クラリスロマイシンの強い苦みと製剤の工夫
- 苦味を強める飲み物、苦みを緩和する飲み物
- さいごに
- 今回の解説のまとめ
すでに登録された方はこちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績