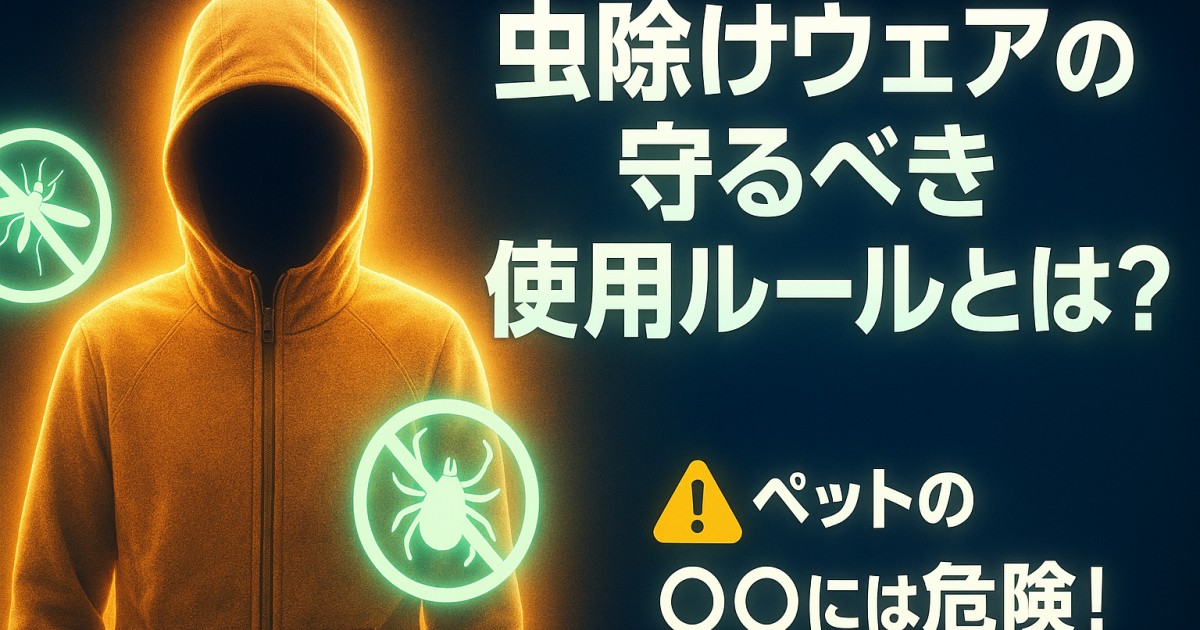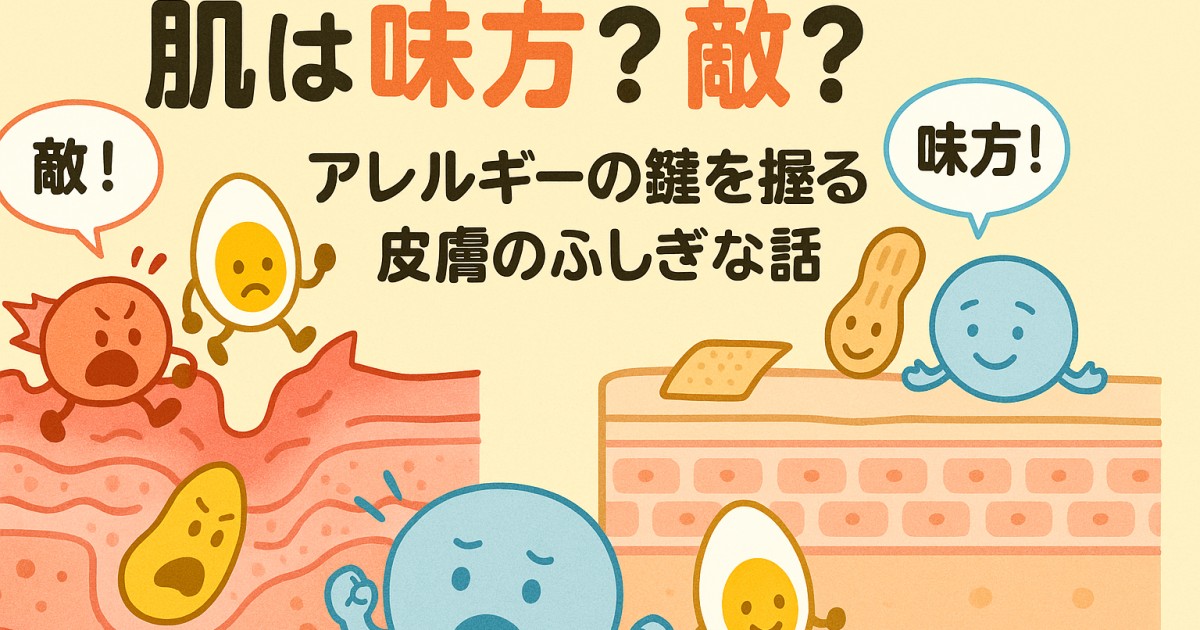「ゲームで脳はダメになる」はウソ?ホント?
小児科で日々奮闘する研修医のA先生。最近、外来で「ゲームばかりだと、子どもの脳は退化するって本当ですか?」と尋ねられ、自信を持って答えられませんでした。そのモヤモヤを抱えて検索した矢先、ある研究のニュース記事が目に留まります。
A先生「ほむほむ先生、少しお時間いいですか? この間、外来でゲームに関する質問にうまく答えられなかった件で、ずっと考えていたんですが…。こんなニュースを見つけたんです。『暴力的なゲームを長時間プレイすると、怒った顔を認識する脳の働きが鈍くなる』という研究で…[1]」
ほむほむ先生「ああ、2019年の研究だね。表情認知への影響は長く続く一方で、攻撃性の上昇は一時的だった、という興味深い報告だった。その研究を読んで、A先生はどう感じたんだい?」
A先生「はい。やっぱりゲームにはネガティブな影響があるんだな、と改めて思いました。そして、以前から聞く『ゲーム脳』という言葉が、保護者の方々の不安の根底にある気がします[2]。一体どこまでが本当の話なのか、混乱してしまって。」
ほむほむ先生「なるほど。A先生が悩むのは大切なことだね。よし、今日は最新の科学的な知見も踏まえて、ゲームと脳の真実について深堀りしようか。」
本記事を最後まで読めば、
・「ゲーム脳」はウソ?ホント?科学的な結論は?
・ゲームの良い影響と悪い影響、最新研究で何が分かった?
・親ができる、ゲームとの上手な付き合い方とは?
これらの疑問にお答えできるよう執筆しました。
「ゲーム脳」の正体は、科学的根拠がなかった

ChatGPTで作画
A先生「まず一番気になっているのが、その『ゲーム脳』という言葉なんです。子どもの頃にも言われていましたが、『ゲームをすると認知症のような脳波になる』なんて、今思うとかなり衝撃的な話ですよね[2]。」
ほむほむ先生「うん、強烈な言葉だったからね。多くの人が不安に思うのも無理はないよ。でも、結論から言おう。この『ゲーム脳』という説は、その後の多くの専門家の検証によって、科学的根拠が乏しい『疑似科学』だったと結論付けられているんだ[3]。」
A先生「えっ、そうなんですか!?疑似科学…ですか?」
ほむほむ先生「そうなんだ。科学論文として最も重要な、専門家による事前チェック、いわゆる『査読』というプロセスを経ていなかったり、実験方法に問題があったりしたんだね。そして何より決定的だったのが、他の研究者が同じ方法で試しても同じ結果にならなかった、つまり『再現性』がなかったこと。科学の世界では、この再現性が信頼性の証だからね。」
A先生「なるほど…。つまり、一人だけが『こうだ!』と言っても、他の誰も同じ結果を確認できなければ、それは科学的な事実とは言えない、ということですね。」
ほむほむ先生「そういうことだね。」
A先生「では、本当の脳科学の世界では、ゲームと脳の関係をどう見ているんですか?」
『ほむほむ先生の医学通信』では、医療の前線で25年以上診療に従事しながら様々な学会で委員を務める小児科医が、医学知識をわかりやすく解説しています。無料登録で定期的に記事をお読みいただけるほか、サポートメンバーにご登録いただくと過去の記事アーカイブすべてにアクセスできます。皆様のサポートを子どもたちの健康に関する研究継続に役立てております。サポート、心より感謝申し上げます。
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績