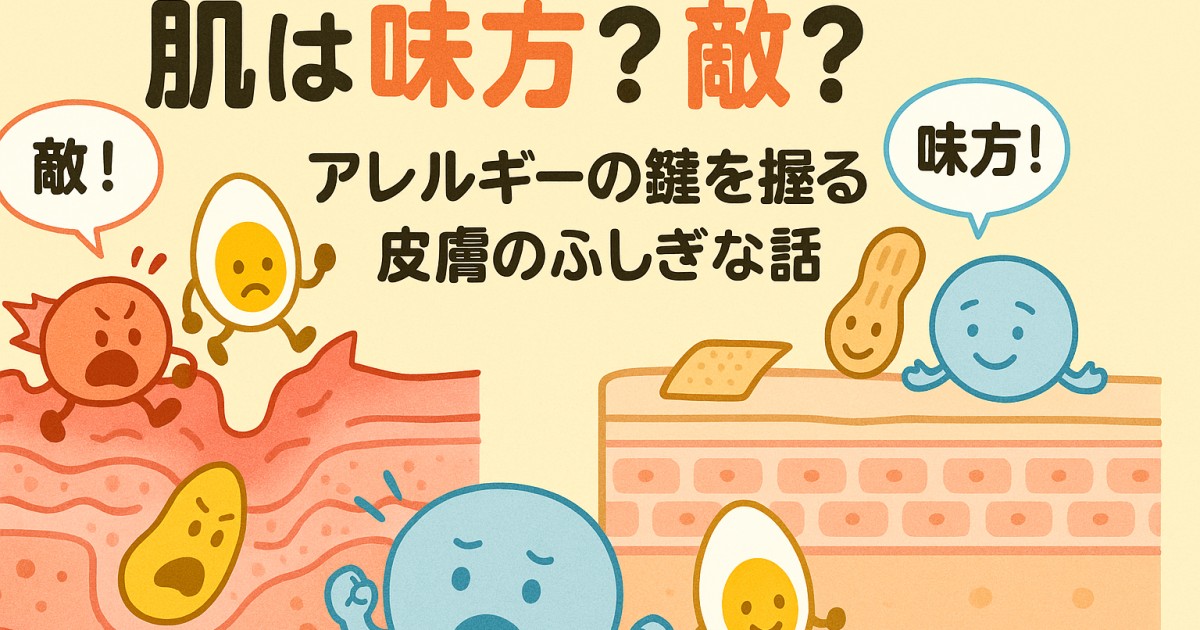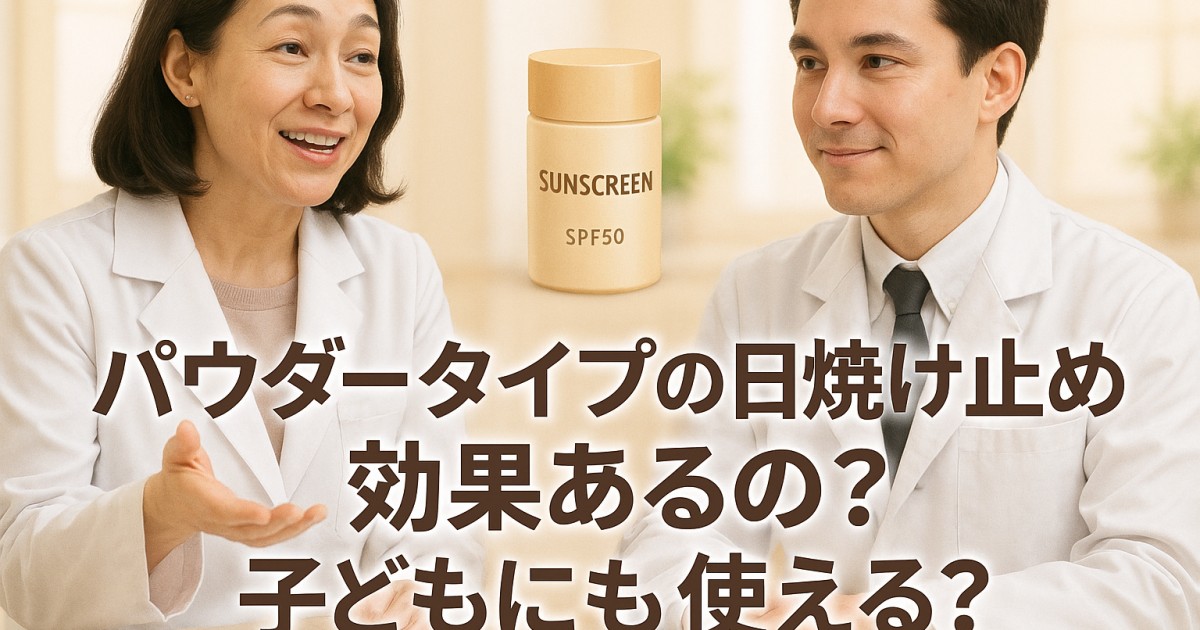アレルギーは遺伝?環境?今できる最新知識
ある日の午後。小児科外来の廊下で、研修医のA先生は、生後数ヶ月のアトピー性皮膚炎の赤ちゃんをあやすお母さんを、少し複雑な表情で見つめていました。診察を終えたお母さんから受けた「私のアレルギー体質が遺伝したんでしょうか」という言葉が、まだ耳に残っています。
『遺伝だから仕方ない、で片付けていいのだろうか...』
でも、A先生の頭には奇妙な記憶がありました。先週診た双子の患者のことです。一卵性双生児なのに、片方には重度の卵アレルギーがあり、もう片方にはまったく症状がなかった。遺伝子が全く同じなのに、なぜ?
そして今朝、別の患者で気になることがありました。両親ともに重度のアレルギー体質なのに、3人の子ども全員にアレルギー症状が出ていない家族。これも遺伝では説明がつきません。
さらに奇妙だったのは、昨日の症例です。アレルギーの家族歴が全くない家庭なのに、重篤な食物アレルギーを発症した子ども。
『一体、何が本当の原因なんだろう...。遺伝はどれくらい関係してるんだろうか…』
そんな思いを抱えながら、A先生は指導医であるほむほむ先生のデスクに足を運びました。ちょうどほむほむ先生は、海外の最新論文に目を通しているところでした。
本記事を最後まで読めば、
・アレルギーは遺伝だけで決まるのか、環境要因の影響は?
・赤ちゃんの肌を守ることが、なぜ食物アレルギー予防につながるのか
・意外な環境要因がアレルギーに与える影響
これらの疑問にお答えできるよう執筆しました。
アレルギー発症は遺伝と環境の"共同作業"

ChatGPTで作画
A先生「先生、今日も親御さんから聞かれました。『アレルギーやアトピー性皮膚炎は、やっぱり遺伝の影響が大きいのでしょうか?』って。正直、どこまでが遺伝で、どこからが環境なのか、はっきり説明できなくて...」
A先生は、診察室での親御さんの不安そうな表情を思い出しながら続けました。
A先生「特に、ご自身がアレルギー体質のお母さんは、本当に申し訳なさそうな顔をされることが多くて。『私のせいで』って自分を責められる方もいらっしゃいます」
ほむほむ先生「A先生、その悩み、よくわかるよ。結論から言うと、遺伝的な要因、つまり"なりやすさ"は確かにある[1]。でも、それが全てじゃない。むしろ最近は、環境要因の重要性も明らかになってきているんだ」
A先生「以前、ご両親ともにアレルギーだと、お子さんの発症リスクが上がるというデータを見たことがあります。でも、それって運命みたいに聞こえて、親御さんに説明するのが心苦しくて...」
ほむほむ先生「その気持ちは大切だね。確かにピーナッツアレルギーに関する双子の研究では、遺伝情報がまったく同じ一卵性双生児が、二人ともピーナッツアレルギーになる確率は約64%という報告がある[1]。これは遺伝という土台の強さを示す数字だよね。でもね、ここで注目してほしいのは、残りの36%は遺伝子が全く同じでもアレルギーにならないということ。そして、二卵性双生児だと一致率は約7%まで下がる[1]。つまり、遺伝子以外の何かが、発症の鍵を握っているってことだよ」
A先生「なるほど!遺伝子が同じでも、結果が違うということは...環境の影響も大きいということか。実は先週診た双子の患者さんも、まさにそのパターンでした。お母さんは『同じように育てたのに、なぜ片方だけ?』って困惑されていて」
ほむほむ先生「その疑問、とても重要だね。実は『同じように育てた』と思っていても、微妙な環境の違いが大きな差を生むことがあるんだ。たとえば、双子でも生まれた順番で数分から数時間の差があるよね。その間の環境の違い、最初に触れた物質、初めての授乳のタイミング...そういった小さな違いが、免疫システムの発達に影響を与える可能性があるんだ。」
A先生「そんな細かいところまで...!じゃあ、親御さんの育て方が悪いわけではないということを、もっとしっかり伝えないと」
ほむほむ先生「その通り。『遺伝子が弾を込め、環境が引き金を引く』という表現があってね。最近の研究では、この"引き金"の正体が、かなりわかってきているんだ」
A先生「引き金の正体...どんなものがあるんですか?」
ほむほむ先生「例えば、子どもの喘息リスクに関わる遺伝子は、普段は静かにしているのに、ライノウイルス、つまり一般的な風邪のウイルスに感染すると、まるでスイッチが入ったように活性化することがある[2]」
A先生「へえぇ!遺伝子って、環境によって働いたり働かなかったりするんだ。まるで、劇場の照明みたいに、スポットライトが当たった時だけ役者が動き出すような...」
ほむほむ先生「面白い例えだね!まさにその通り。遺伝子も"状況次第"で働き方が変わる。だから、その『スポットライト』をコントロールできれば、予防の可能性が見えてくるんだよ」
A先生「そういえば昨日、3人兄弟のうち真ん中の子だけアレルギーがひどい家族がいました。お母さんは『上の子と下の子は大丈夫なのに、なぜこの子だけ?』って。今の話を聞くと、その子が生まれた時期や環境に何か特別な要因があったのかもしれませんね」
ほむほむ先生「鋭い観察だね。実は最近、もっと意外な環境要因も見つかってきているんだ」
この記事は、無料会員向けとして公開しておりますが、次の記事が完成次第(数日から1週間以内の予定です)、サポートメンバー限定に移行いたします。無料公開中はコメントを閉じておりますが、サポートメンバー限定に移行してからは公開いたします。サポートメンバーの方々からのコメントをお待ちしております。
『ほむほむ先生の医学通信』では、医療の前線で25年以上診療に従事しながら様々な学会で委員を務める小児科医が、医学知識をわかりやすく解説しています。
無料登録で定期的に記事をお読みいただけるほか、サポートメンバーにご登録いただくと過去の記事アーカイブすべてにアクセスできます。
皆様のサポートを子どもたちの健康に関する研究継続に役立てております。サポート、心より感謝申し上げます。
この記事は無料で続きを読めます
- 運命の分かれ道は?「皮膚」「食事」そして「腸」にある?!
- 【新常識①】アレルギー予防は「塗る」から始める、でも「洗う」も大切
- 【新常識②】常識が逆転?アレルギーになりやすい食べ物ほど「早く会わせる」、でも多様性も鍵
- 知っておきたい、その他の重要な環境要因
- 環境汚染という見えない敵
- 実践的な3つのアドバイス
- 進化する未来の戦略
- まとめ
- 参考文献
すでに登録された方はこちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績