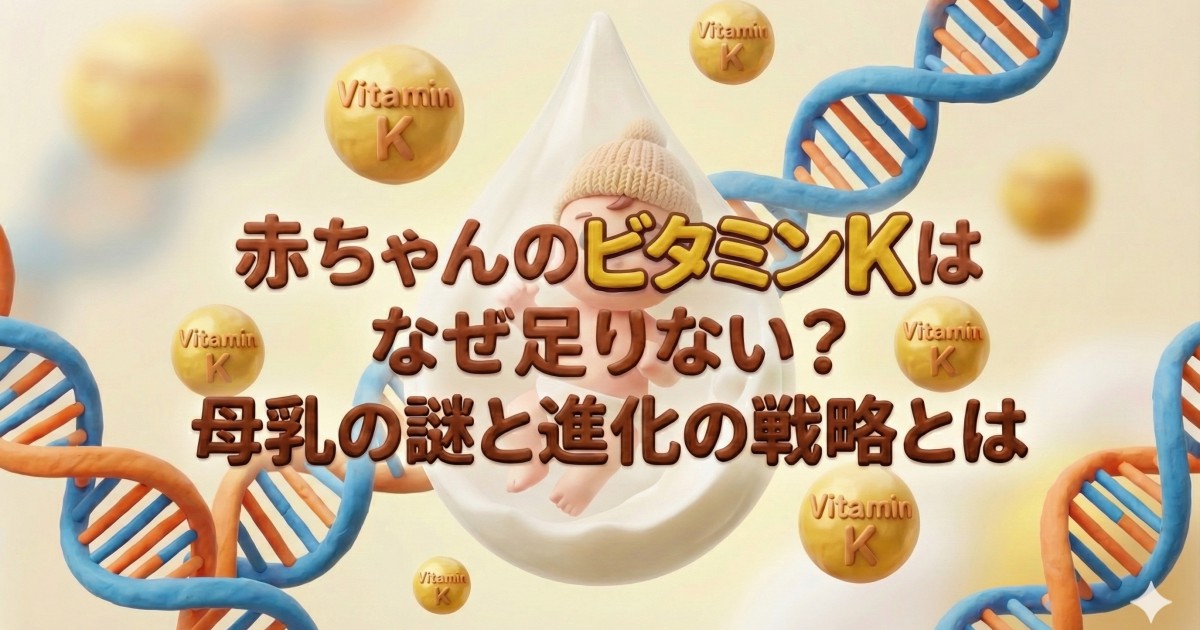新生児からの保湿、結局どうなの?アトピー予防の大論争に専門医が答える
こんにちは。最近は本文のみでも1万文字以上、参考文献を含めると15000文字以上になっていますが、持てる力の全てを注ぎ込んで、深堀りして、でもわかりやすい記事をお届けしようと頑張っています。感想などをSNSなどで呟いていただけると小躍りして喜びます。
今回の記事は、サポートメンバー限定記事ですが、最初の6割くらいまで無料で読むことができます。よろしければ、サポートメンバーもご考慮いただければ幸いです。
小児科研修医として奮闘するA先生は、最近の悩みを抱えていました。外来で赤ちゃんのスキンケアについて質問されるたび、自信を持って答えられないのです。
「アトピー予防に保湿が良いって聞きましたけど、本当ですか?」
「保湿剤は、どれを選んだらいいんでしょう…?」
切実な親御さんの問いに、明確な指針を示せずにいました。新生児からの保湿剤、数年前に推奨されていたかと思えば、大規模な研究で否定されたという話も聞いたような…。
「一体、何を信じて、どう伝えればいいんだろう…。」
A先生は、指導医のほむほむ先生のデスクを訪れました。
本記事を最後まで読めば、
・アトピー予防の考え方がどう変わってきたか
・保湿ケアを巡る大論争の現在は?
・今日から実践できる正しい保湿ケアの秘訣
これらの疑問にお答えできるよう執筆しました。
アトピー予防の常識が変わった?「外から守る」という発想

ChatGPTで作画
A先生「ほむほむ先生、お忙しいところすみません!今、ちょっとよろしいでしょうか?」
ほむほむ先生「おや、A先生。もちろん、どうしたんだい?悩んでいるような顔をしているね」
A先生「先生、お見通しですね。最近、外来で新生児の保護者の方からアトピー予防の保湿ケアについてよく質問されるんですが、情報が色々ありすぎて…。以前、すごく熱心に保湿をされていたのに、食物アレルギーになってしまった赤ちゃんの親御さんから、『私のやり方が悪かったんでしょうか』と言われてしまって…。最新の考え方を、先生にしっかり教えていただきたいんです!」
ほむほむ先生「そうか…。それは辛い経験をしたね。確かにこの分野は、ここ十年で研究結果が目まぐるしく変わってきたから、混乱するのも無理はない。よし、一緒に最新の知見まで整理していこうか。まず大前提として、アトピー性皮膚炎になるお子さんが世界的に増えている、という状況があるんだ。」
A先生「はい、だからこそ、予防がすごく重要なんですよね」
ほむほむ先生「その通り。かつて、予防の主役は『アレルゲン回避』だった。つまり、アレルギーの原因になりそうな卵を食べる時期を遅らせたり、お家のホコリやダニを徹底的に排除したり…いわば“敵”を家に入れない作戦だね。でも、大規模な研究を重ねても、残念ながらアレルゲン回避ではアトピーや食物アレルギーの発症を予防できるという証拠は得られなかったんだ[1][2]」
A先生「そうだったんですね…。学生の頃は、まだアレルゲン回避が主流だったような気がします」
ほむほむ先生「うん、無理もないよ。大きな転換点が訪れたのは2000年代の半ば。皮膚の“壁”の役割を担う『フィラグリン』という遺伝子の変異が、アトピー性皮膚炎の発症に深く関わっていることが突き止められたんだ[3]」
A先生「フィラグリン遺伝子。以前お話で聞いたことあります。肌のバリア機能の要ですよね。この遺伝子に変異があると、生まれつき肌が乾燥しやすかったり、外部からの刺激に弱かったりするんですよね。」
ほむほむ先生「この発見で、考え方が変わってきたんだね。『敵を避けるより、まず家の“壁”である皮膚バリアを頑丈にすればいいんじゃないか』とね。その『目に見えない個人差』を何とか可視化できないかと思ってね。実は、僕達の研究で、生まれてすぐの赤ちゃんの額から蒸発する水分量を測るという研究をしているんだ。いわゆる経表皮水分蒸散量(TEWL)というものなんだけど、その数値が高いと、将来アトピー性皮膚炎になるリスクが有意に高いことが示されたんだよ[4]」
A先生「えっ、その研究を先生が!?生まれてすぐの肌の乾燥具合で、将来が予測できるんですか!?見た目はみんなツルツルに見えるのに、そんなに個人差があるなんて…」
ほむほむ先生「そうなんだ。目に見えないレベルで、バリア機能には個人差がある。そして、その壁の性能が下がっていると、外から色々なものが侵入しやすくなる…A先生なら、どうなるか想像がつくかな?」
A先生「なるほど!壁が弱くなっていると、そこからホコリや食べ物のカスといったアレルゲンが皮膚の中に侵入してしまう…。そして体がそれを“異物”だと認識して、攻撃準備を始めてしまうってことですね」
ほむほむ先生「その通り。その現象を『経皮感作(けいひかんさ)』と言う…って、解説したことがあったね[5]。この経皮感作こそが、アレルギー反応の最初の引き金になるんじゃないか、という考え方が生まれた。これが『アウトサイド・イン仮説』だよ[6]」
A先生「アウトサイド・イン…。つまり、体の“外側”の問題が“内側”のアレルギーを引き起こす、という流れですね!腑に落ちました。じゃあ、その“壁”を保湿剤でしっかり補強してあげれば、アトピーも、その先の食物アレルギーやぜんそくといった『アレルギーマーチ』も防げるかもしれない、と期待されたわけですね!」
ほむほむ先生「その通り。でもね、A先生。覚えておいてほしい。この『保湿で壁を補強する』、すなわち保湿剤を塗るという方法が、論争を巻き起こすことになるんだ。そして、そこには思わぬ“落とし穴”も潜んでいたんだよ」
A先生「落とし穴…ですか?」
ほむほむ先生「うん。その話は、また後でゆっくりしよう。まずは、希望の光が見えた時代、とはいってもほんの10年ほど前の話からだ」
「保湿ケアでアトピーが防げるかも」と世界が沸いた2014年

ChatGPTで作画
A先生「その期待を後押しするような研究が、確か2014年に立て続けに発表されて、話題になりましたよね?」
ほむほむ先生「よく勉強しているね!その通り。一つは、僕たちのチームが日本で行った研究なんだ。ご両親のどちらかがアトピー性皮膚炎を持つような、発症リスクが高いと考えられる新生児118人を対象にしたものだった[7]」
A先生「えっ、先生!あの論文、先生が…!?続けてください!」
ほむほむ先生「ありがとう。僕たちは、生後すぐから毎日、乳液タイプの保湿剤を全身に塗るグループと、特に何もしないグループを比べたんだ。すると、生後32週の時点で、保湿剤を塗ったグループのアトピー性皮膚炎や湿疹の発症リスクが、約3割低下したんだよ[7]」
A先生「3割も。ご自身の研究でそれを証明されたなんてすごいですね!当時は盛り上がったでしょうね!」
ほむほむ先生「ああ、『ついに有効な予防法が見つかったかもしれない!』ってね。しかも、海外の有名な医学雑誌の同じ号に、アメリカとイギリスの合同チームから、シンプソン先生たちによる同様の研究報告もあったんだ[8]」
A先生「はい、そちらの論文も読んだ記憶があります。確か、こちらもインパクトのある結果でしたよね」
ほむほむ先生「そうなんだ。こちらもリスクの高い新生児120人が対象だった。生後3週間以内に、市販のワセリンベースの保湿剤などを1日1回以上塗ってもらったところ、生後6ヶ月時点でのアトピー性皮膚炎の発症リスクが、保湿したグループで半分にまで低下したんだ」
A先生「半分ですか!?国も違えば、使った保湿剤の種類も違う可能性もあるのに、それでも同様の良い結果が出たことで、『シンプルな保湿ケアでアトピー性皮膚炎が予防できるかもしれない』という希望が一気に世界中に広がったってことですね。」
ほむほむ先生「うん。多くの小児科医や親御さんが、この明るいニュースに希望を抱いた。僕もその一人だったよ。でも、科学の世界は、そんなに単純には終わらなかったんだ」
まさかのどんでん返し?大規模研究がもたらした「効果なし」という衝撃
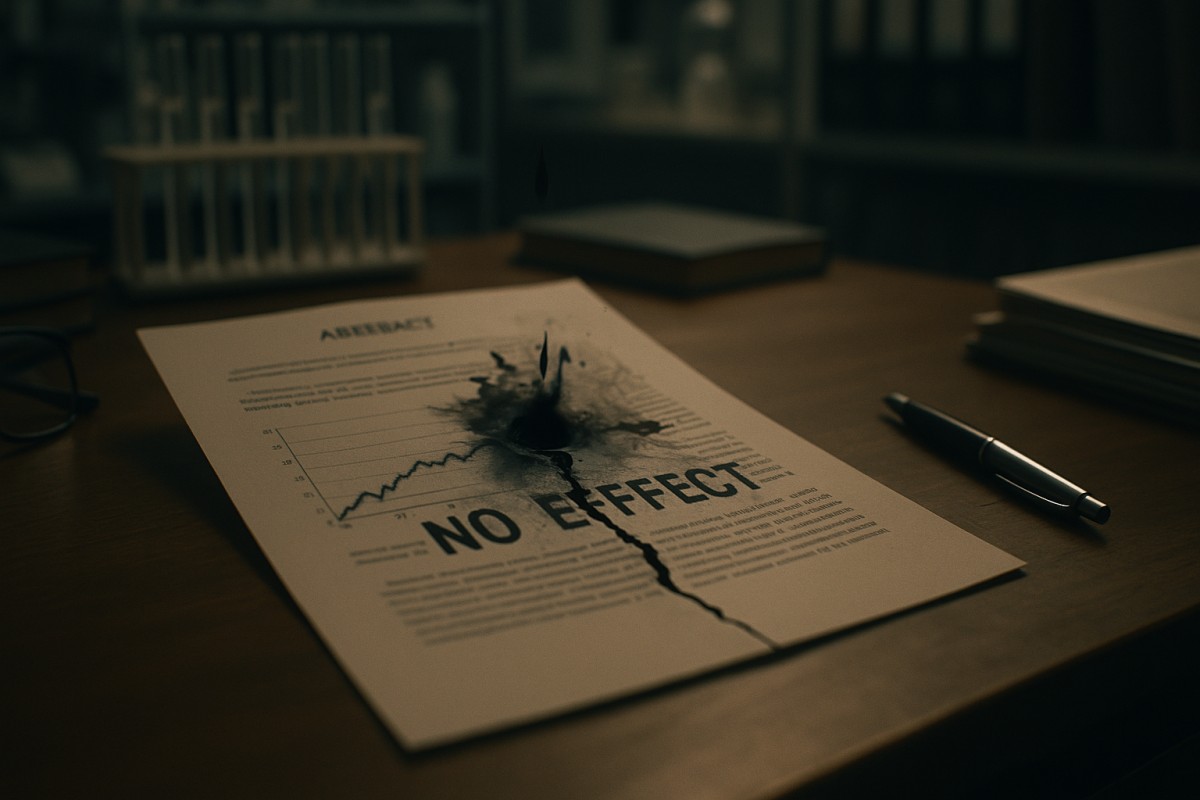
ChatGPTで作画
A先生「物語はここで終わらなかったんですね?混乱しているのは、まさにこの後の展開なんです。あの希望に満ちた結果が、数年後にはひっくり返されてしまうなんて…」
ほむほむ先生「その通りだ、A先生。希望に満ちた結果を受けて、『これは本当なのか、もっと大きな規模の研究で白黒つけよう』という動きが世界中で起きた。ところが、その結果は誰もが予想しなかったものだったんだ」
A先生「というと…?」
ほむほむ先生「その代表格が、2020年にイギリスのChalmers先生たちが報告した『BEEP試験』だ。これは当時として過去最大規模の研究だった。アトピーなどの家族歴があるリスクの高い赤ちゃんを、約1400人も集めて行われた[9]」
A先生「1400人!先程の研究の10倍以上…桁が違いますね」
ほむほむ先生「そうなんだ。片方のグループには生後1年間、毎日保湿剤を塗るように指導し、もう片方は通常のスキンケア指導だけ。そして2歳になった時点でのアトピー性皮膚炎の有病率を比べたんだが…」
A先生「(ゴクリ…)結果は、どうだったんでしょう?」
ほむほむ先生「驚くべきことに、保湿剤を使ったグループと使わなかったグループで、統計的に意味のある差は認められなかった。つまり、予防効果は確認できなかった、という結論だった」
A先生「ええっ!?あれだけ期待されていたのに、効果なし、ですか…。信じられない…。じゃあ、信じてきたことは、全部間違いだったってことですか…?」
ほむほむ先生「それだけじゃないんだ。さらに追い打ちをかけるように、保湿剤を毎日塗っていたグループの方が、皮膚の感染症、例えば“とびひ”なんかを起こすリスクが、わずかではあるけれど統計的に高くなってしまった」
A先生「うわあ…予防どころか、むしろリスクが上がるなんて…。現場は混乱したんじゃないでしょうか?親御さんに『良かれと思ってやったのに』と責められてしまいそうです…」
ほむほむ先生「そうだね、混乱したのは確かだね。この結果を受けて、BEEP試験の研究チームは『アトピー予防目的で新生児に日常的に保湿剤を使うことは推奨すべきではない』と結論を出したんだ。初期の研究とは真逆の結果に、世界中のガイドラインが見直しを迫られる事態になったんだ」
A先生「なるほど…。だから一時、『保湿は意味がない』という論調が強まったんですね。同じ頃の北欧の『PreventADALL試験』というのも、少し複雑な結果だったような…」
ほむほむ先生「そうだね。あれは約2400人対象の、これまた大規模な研究だったんだけど、保湿が顔だけだったり、指示通りにケアを続けられた人の割合が決して高くなかったりと、結果の解釈が少し難しい面もある[10]。ただ、やはりスキンケアによる明確な予防効果は示されなかった。これらの結果は、僕たち専門家にとっても本当に大きな衝撃だったよ。『なぜ小規模では効いたのに、大規模では効かないんだ?』と、世界中の研究者が頭を抱えたんだ」
A先生「うーん、考えれば考えるほど分からなくなります…」
ほむほむ先生「気持ちは分かるよ。でも、A先生、ここで思考停止してはいけない。なぜ違う結果が出たのか?を考えることこそ、僕たち臨床家にとって一番大事なことなんだ。実際、このBEEPショックの後、2022年にZhong先生らが出したメタアナリシス、つまり過去のたくさんの研究をまとめて解析した研究では、『一概に効果なしとは言えない。ハイリスクの赤ちゃんに、評価時点まで介入を継続した研究では有効性が示唆される[11]』という、もう少し緩やかな結論も出ているんだよ。つまり、単純な白黒ではなく、なにか条件があるんじゃないかと考えられるようになったんだ」
A先生「条件付きの有効性、ですか。なるほど、少し光が見えてきました」
ほむほむ先生「そう。科学というのは、こうやって一進一退を繰り返しながら、少しずつ真実に近づいていくものなんだ。BEEPショックの後、専門家たちは考えた。『もしかしたら、やり方が悪かっただけじゃないか?介入するタイミングと期間、そして使う保湿剤の種類が、もっと重要なんじゃないか』とね」
A先生「タイミングと期間、そして種類…ですか?」
ほむほむ先生「そして、また大きな”科学のどんでん返し”が起こるんだ。さらには、気をつけなければならない点が見えてくることになる」
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績