アレルギーの犯人「IgE」を追え!謎の物質を追った日本人夫妻の物語
こんばんは。皆さんお元気でしょうか。前回の更新から6日経ってしまいました。日常診療も多忙になりつつ、さらに9月の終わりから10月にかけて学会が多いこと、研究の準備や論文、査読の依頼が立て込み、ニュースレターにどうしても時間が取れませんでした…。
しかし、なんとか書き上げました!
実は今回はコラム的に短めにしようと思っていたのですが、本文のみで9000文字以上になりました。
それはさておき、皆さんが「アレルギー検査といえばこれ!」という人が多いであろう「IgE抗体検査」。この発見には日本人の研究者夫妻とドラマが隠されているのです。さて、どんなドラマなんでしょうか。一緒に深堀りしてまいりましょう。
今回も、数日間から1週間ほど無料公開、その後はサポートメンバー限定に変更する予定です。
(2025年9月27日16:30 次の記事が完成しましたのでサポートメンバー限定に変更しました)
前回の記事も、さまざまな嬉しいポストをありがとうございます!
とっても励みになっております!!

今回もスゴすぎて、いっきに目が覚めました笑
読み手が理解できやすいよう、例えを上手に使われ優しく解説
さらに大切なところ、誤解を招く恐れがあるところは太字で強調してくださってる、優しいニュースレターです😌

日焼けも気になるけど、日光浴によるビタミンDも大切。
バランスをとりながらうまく付き合っていきたい☀️
そして、生まれた後でもケアできる内容を紹介してくれているのが嬉しい☺️
ある日の午後、研修医のA先生は、アレルギー専門医である指導医のほむほむ先生のもとへ、医学雑誌のコピーを手に駆け寄りました。その目には、知的好奇心と興奮の色が浮かんでいる。
「先生、ちょっとよろしいですか?今、アレルギーの歴史について調べていたら、IgE抗体の発見物語が面白すぎて…!まるで壮大な科学ミミステリーじゃないですか。私達は当たり前のように血液検査でIgEの値を測定していますけど、こんなドラマがあったなんて、全く知りませんでした」
ほむほむ先生は椅子を勧めながら、にこやかに頷いた。
「A先生、とても良いところに目を付けたね。そうなんだよ。アレルギーの主役ともいえるこの分子がどうやって見つかったのか、その背景には壮大なドラマが隠されているんだ。我々の大先輩である夫妻は、実は僕がはじめて英語論文を書き上げるためにお世話になった恩師である斎藤博久先生の恩師の方なんだ。だから僕もIgE抗体は普段から研究対象なのかもしれない…というのはひとまずおいておいて。せっかくだから今日は、その謎解きの旅に一緒に出かけてみようか。アレルギーの正体を探る長い探求の末に医療の常識を覆した、歴史的な発見の物語なんだ」
本記事を最後まで読めば、
・アレルギーの主役「IgE抗体」のユニークな正体
・謎の物質「レアギン」を巡る世紀の発見物語
・IgE発見がもたらした診断・治療の革命と未来
これらの疑問にお答えできるよう執筆しました。
免疫の特殊部隊と、変わり者の「IgE」
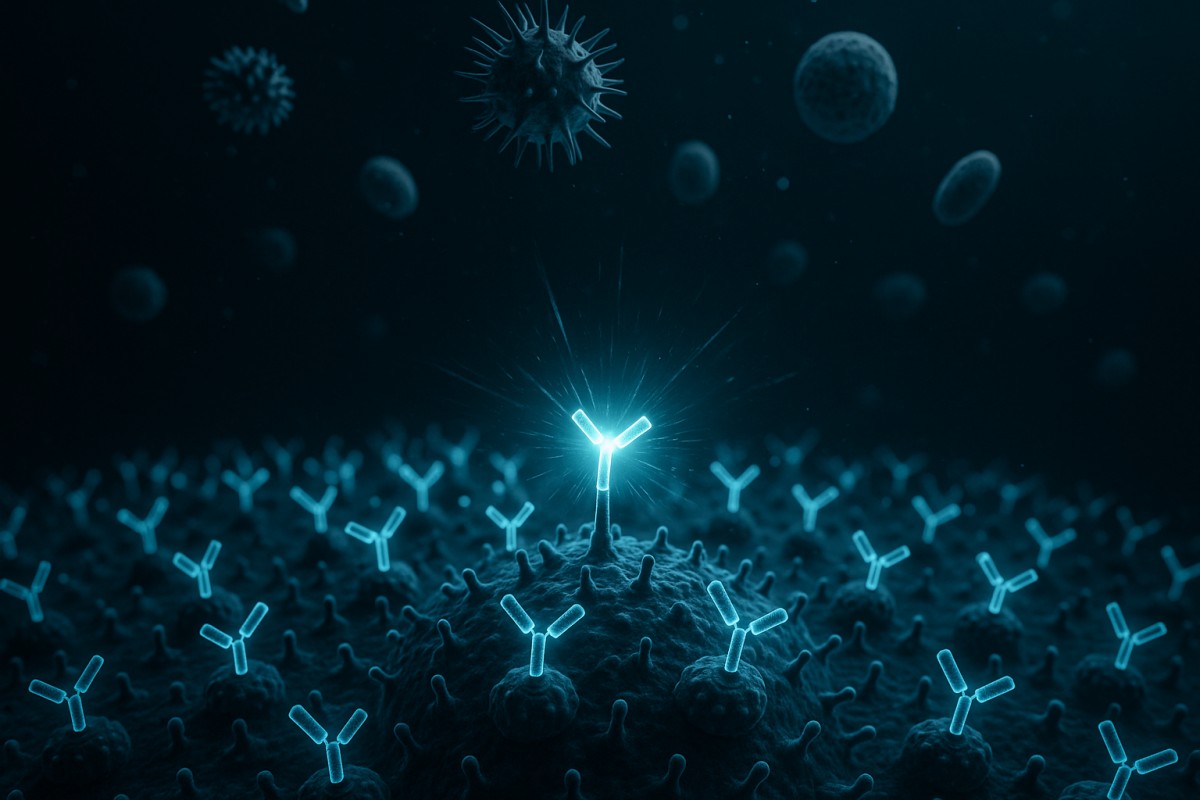
ChatGPTで作画
A先生「早速ですが、我々の体にある『抗体』って、体内に侵入してきたウイルスや細菌と戦う、いわば免疫システムの特殊部隊ですよね?ヒトには主に5つのクラス(IgG, IgA, IgM, IgD, IgE)があると習いましたが[1]、その中で、どうして『IgE』だけがこんなに特別で、アレルギーの“悪役”のように扱われることがあるんでしょうか?」
ほむほむ先生「うん、良い質問だね、A先生。そこから始めよう。その通り、抗体は体内に侵入してきた異物、つまり『抗原』を見つけてやっつける、頼もしい『特殊部隊』だ。5つの部隊(クラスという)があるけど、その中でもIgEはとびきりの変わり者、と言えるかもしれないな」
A先生「変わり者、ですか?具体的にどういうところが…?なんだか、他の抗体と比べて構造が『柔軟』なイメージがあるんです。IgGなんかはカチッとした鍵と鍵穴のイメージですけど、IgEはもっとこう…しなやかに形を変えるような…」
ほむほむ先生「お、鋭いね!その『柔軟さ』という直感、実は重要なキーワードなんだ。それは後の話においておいて、まずは一番分かりやすい変わり者ポイントは、その『量』なんだよ。血液中のすべての抗体をかき集めても、IgEが占める割合はわずか0.002%以下。資料によっては0.0001%未満とも言われるほどなんだ[2]」
A先生「ええっ、そんなに微量なんですか!?主力部隊であるIgGの、文字通り桁が何個も違う少なさですね…。それなのに、アレルギー反応では主役級の働きをするなんて…なんだか不思議です。まさに少数精鋭の特殊部隊、という感じでしょうか?」
ほむほむ先生「うまいこと言うね!その通りで、微量でも、強い生物学的な活性を持っているんだ。実は、IgEはもともと、回虫のような寄生虫から体を守るために進化したと考えられているんだよ[3]。だから今でも、寄生虫に感染するとIgEの値がぐっと増えることがある」
A先生「なるほど!本来は寄生虫という巨大な敵と戦うための専門部隊だったんですね。以前、担当した患者さんで、好酸球とIgEがすごく高い方がいて、まさかと思ったら本当に寄生虫の感染だったことがありました。あの時の数値の上がり方は尋常じゃなかったです…」
ほむほむ先生「そうだろう。臨床現場の経験と知識が繋がると、理解が深まるよね。IgEとマスト細胞のコンビが、寄生虫だけじゃなくヘビの毒などから体を守る役割も担ってきた可能性も示唆されているんだよね[4]。ただ、衛生環境が劇的に向上して、寄生虫と戦う機会がなくなった現代の日本では、IgEは本来戦うべき相手を見失いがちになっている。その結果、花粉や食物といった、本来は無害なはずのものに過剰反応してしまう。これこそが、アレルギーの“誤作動”の正体のひとつなんだ」
A先生「平和な時代に、強力な武器を持った部隊が目標を見失って暴走している、みたいなイメージですかねえ…。それで、IgEの最大の特徴って何でしたっけ?確か、他の抗体と違って、特定の細胞にくっついて待ち伏せする、という点でしたよね?」
ほむほむ先生「よく勉強しているね。IgEの最大の特徴は、マスト細胞や好塩基球といった特殊な免疫細胞の表面にある、専用のドッキングポート、専門的には『高親和性Fcε受容体』というんだけど、そこに他の抗体の100倍から1000倍も強力にくっついて、じっと待機している点なんだ[5]」
A先生「血液中をパトロールするんじゃなくて、重要な拠点である細胞の上で、敵が来るのを待ち構えている…。なんだか、まるで地雷みたいですね…」
ほむほむ先生「その例え、すごく分かりやすいね。まさしく地雷といえるね。アレルゲンが体内に入ってきて、この待機しているIgEの『信管』にカチッとはまった瞬間、マスト細胞という“火薬庫”からヒスタミンなどの化学伝達物質が一斉に放出される。これが、くしゃみ、鼻水、じんましんといった即時型アレルギー反応の引き金になるんだ。アレルギー専用の、超即効性スイッチと言えるかもしれないね」
A先生「なるほど…。でも、寄生虫と戦うための強力な武器が、なぜ花粉や食べ物に誤作動してしまうのか、その『スイッチの切り替え』みたいな部分が、まだピンとこないんです。何かきっかけがあるんでしょうか?」
ほむほむ先生「うん、そこがアレルギー研究の最も面白く、そして難しい部分だね。その『スイッチ』の仕組みこそが、IgEの光と影、両方の側面を理解する鍵になるんだ。そして、そのスイッチが実は一つじゃないかもしれない、という話も…。これは後で話そうか。まずは、この不思議なIgEが、どうやって歴史の表舞台に登場したのかを見ていこうか」
謎の物質「レアギン」の正体を追え!
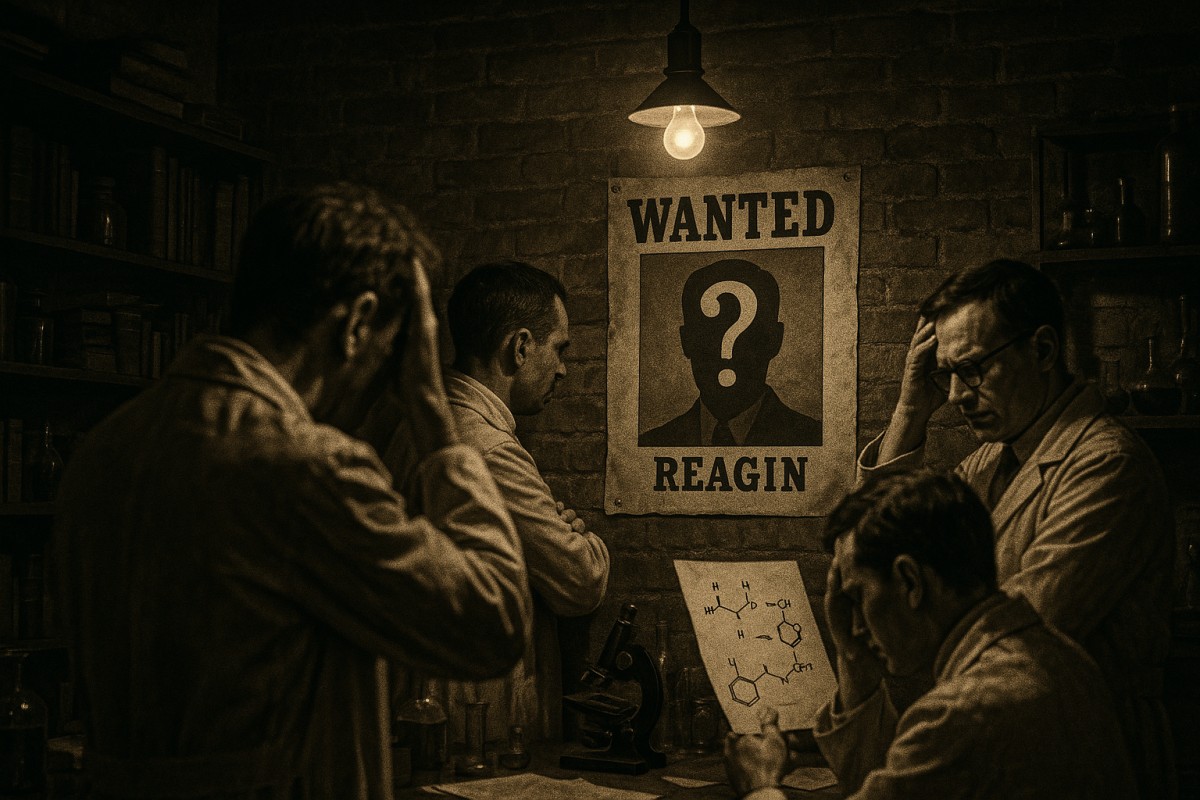
ChatGPTで作画
A先生「はい!そもそも、このIgEが見つかる前、昔の先生方はアレルギーをどう考えていたんですか?1906年にオーストリアのフォン・ピルケ医師が『アレルギー』という言葉を提唱したのが始まりなんですよね[6]。『アレルギー(allergy)』はギリシャ語の allos(他の) と ergon(作用/反応) に由来していて、直訳すると『変化した反応性』という意味で、免疫が必ずしも体を守る良いことばかりではない、という偉大な気づきの始まりだった、と」
ほむほむ先生「その通り。そして1921年、歴史を大きく動かす、ある有名な実験が行われたんだ。ドイツのプラウスニッツとキュストナーによる実験だ。魚アレルギーを持つキュストナーさんの血清を、アレルギーのないプラウスニッツさんの皮膚に注射した。そして、その場所に魚のエキスを注射したら…なんと、プラウスニッツさんの皮膚に、キュストナーさんと同じアレルギー反応、つまり膨疹が出たんだ[7]」
A先生「えっ、ご自身の体で実験したんですか!?研究者の執念というか、真理を探究する情熱を感じますね…!」
ほむほむ先生「本当にそうだよね。今の倫理観では到底考えられない実験だけど、この『プラウスニッツ・キュストナー反応(PK反応)』によって、アレルギー症状が血清に含まれる“何らかの液体性の因子”によって人から人へ伝わることが、動かぬ証拠として証明されたんだ。そして、この謎の因子は、アレルギー反応(reaction)にちなんで『レアギン(reagin)』と名付けられたんだよ[8]」
A先生「レアギン…。初めて聞く名前です。なんだか響きがミステリアスですね」
ほむほむ先生「うん。このレアギンは、熱に弱いとか、注射した皮膚の場所に長く留まる、といった性質は分かっていたんだけど、その正体は何十年も謎のままだった。1960年代までに、先ほど話したIgG、IgA、IgM、IgDという他の4つの抗体クラスは次々と発見されていたのに、レアギンの性質はどれとも一致しなかった。まさに科学者たちを悩ませる『ミッシングリンク』、失われた環だったんだね」
A先生「正体不明の犯人が、アレルギーという事件を引き起こしていることは分かっているのに、誰もその姿を捉えられない、という状況だったんですね。当時の臨床現場では、治療はどうしていたんでしょう?」
ほむほむ先生「そうだね、原因物質が分からないから、治療は対症療法が中心。例えば、アナフィラキシーショックにはアドレナリンを使ったり、じんましんには抗ヒスタミン薬が開発されたりした。そして、もう一つ、今のアレルゲン免疫療法の原型になる『減感作療法』も始まっていたんだ[9]。」
A先生「減感作療法!原因となるアレルゲンを少しずつ投与して、体を慣らしていく治療法ですね。でも、レアギンの正体が分かっていないのに、どうしてそれが有効だと考えられたんでしょう?」
ほむほむ先生「1911年にはもう臨床的な有効性が報告されていたんだけど、なぜ効くのか、そのメカニズムは全くの謎だったんだ。いわば、“経験的に有効だと分かっているが、理由は説明できない”という状態が、半世紀以上も続いたんだよ。臨床医たちは、見えない敵に対して、手探りで戦っていたようなものだったんだ」
A先生「でも、1960年代になって、ついにその膠着状態が動き出すんですね!」
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績











