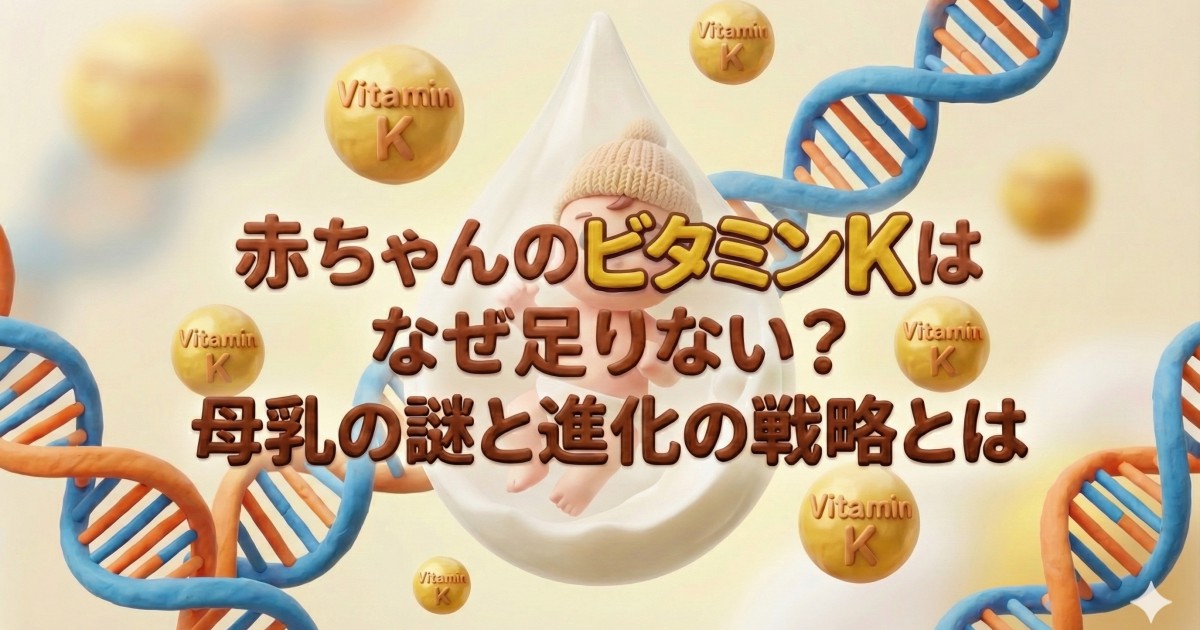【ノーベル賞受賞】「Treg細胞」の謎に迫る~アクセルとブレーキ?免疫の暴走を止める~
こんにちは。2025年のノーベル賞の受賞者に大阪大学特任教授の坂口志文先生と京都大学特別教授の北川進先生が選ばれました。誇らしいことですね。特にTregに関しては、私のようなアレルギー専門医にとっても考えることが少なくない細胞です。でも、Treg細胞って、どんな働きをしているのか、わかりにくいですよね。そこで今回は「誰でも読める記事」でお届けします。今後も、このような医学に関する深堀り記事を定期的に配信していますので、よろしければ登録いただけましたら幸いです。
ある日の昼下がり。小児科のカンファレンスルームは、窓から差し込む柔らかな光で満たされている。しかし、研修医のA先生は、タブレットの画面に釘付けになり、興奮を隠しきれない様子で指導医のほむほむ先生に駆け寄った。
A先生「先生、見ましたかこの記事!大阪大学の坂口志文先生たちが、2025年のノーベル生理学・医学賞を受賞されたそうです!」
タブレットには、「免疫反応抑える『制御性T細胞』を発見」という見出しが躍っている[1]。
ほむほむ先生「おお、本当だ!ついにこの日が来たんだね。A先生が心を動かされるのもよく分かるよ。僕達が日々向き合っている病気の根幹に関わる、素晴らしい発見だからね。未来への希望の鍵のひとつが、このノーベル賞のテーマである『Treg細胞(ティーレグ細胞)』なんだ。この細胞はね、免疫という複雑なオーケストラを指揮する、冷静沈着な指揮者のような存在なんだよ。その発見には壮大なドラマがあり、働きを知れば、アレルギーからがん治療まで、医療の未来がぐっと鮮やかに見えてくるはずだ。」
本記事を最後まで読めば、
・免疫の暴走を止める「指揮者」の正体とは?
・なぜ「幻の細胞」と呼ばれ、発見が困難だったのか?
・Treg細胞が切り拓く、未来の医療の可能性とは?
これらの疑問にお答えできるよう執筆しました。
免疫システムの絶妙な指揮者「Treg細胞」とは?
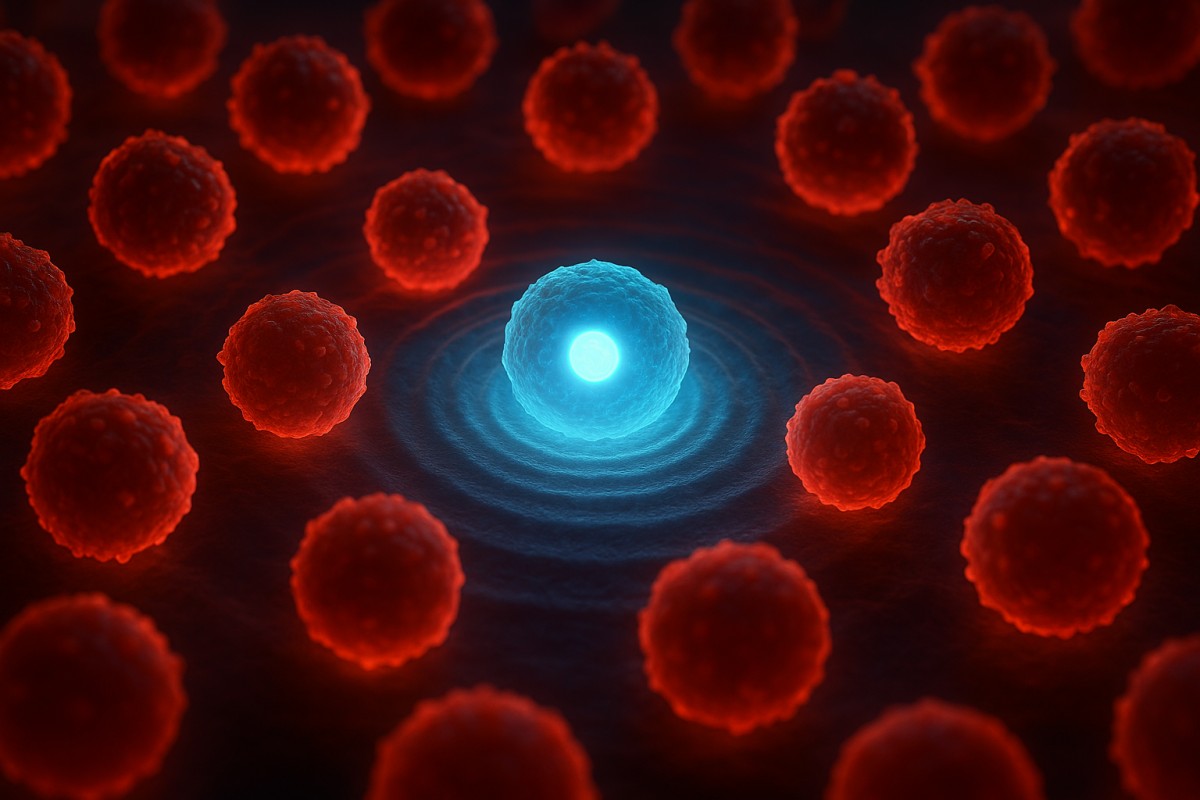
ChatGPTで作画
A先生「先生、先ほどお話に出た『制御性T細胞』、通称Treg(ティーレグ)細胞について、さっそく教えていただきたいです!『免疫のオーケストラの指揮者』という言葉に引き込まれました。」
ほむほむ先生「うん、いいところに目を付けたね。私たちの免疫システムには、ウイルスに感染した細胞やがん細胞を直接攻撃する『キラーT細胞』のように、力強く演奏する“金管楽器”の奏者がたくさんいるんだ[2]。彼らは非常に頼もしいけれど、情熱のあまり、時に音が大きすぎたり、間違った楽譜を演奏し始めたりすることがある。」
A先生「なるほど!アクセル全開の攻撃部隊ですね。でも、それだけだと不協和音になってしまう…。」
ほむほむ先生「その通り。そこで指揮者であるTreg細胞が登場する。彼らは『そこ、少し音量を抑えて!』とか『君の出番はまだだよ』とタクトを振り、全体のハーモニーを整えるんだ。攻撃部隊がやり過ぎたり、うっかり自分の正常な細胞を敵だと勘違いして攻撃し始めたりしないように、絶妙なバランスを保っている大切な存在なんだよ。」
A先生「アクセルとブレーキというより、もっと能動的で、知的な役割なんですね。その指揮者、Treg細胞は、他の免疫細胞とどこが違うんでしょうか?」
ほむほむ先生「いい質問だね。Treg細胞はT細胞の中でも『CD4陽性T細胞』というグループに分類される。そして、細胞の表面に『CD25』という分子がたくさん出ているのが、古くからの目印の一つだったんだ[3]。ただ、厄介なことに、このCD25は“情熱的に演奏している”攻撃的なT細胞にも多く見られるから、昔はこれだけで指揮者を見分けるのが非常に難しかったんだよね。」
A先生「つまり、CD25という目印だけでは、熱心な奏者なのか、冷静な指揮者なのか、区別がつかなかったということですね。」
ほむほむ先生「そういうこと。そこで決定的となったのが、細胞の核の中で働く『Foxp3(フォックスピースリー)』という“指揮者としての魂”とも言えるタンパク質の発見なんだ[4]。このFoxp3こそが、Treg細胞を真の指揮者に育て上げる、いわば彼らのタクトそのものなんだよ。」
A先生「Foxp3…!それが、Treg細胞のアイデンティティなんですね。なんだか、少しずつ指揮者の正体に近づいてきた気がします!」
幻の細胞? Treg細胞発見までの長く険しい道のり
A先生「これほど重要なTreg細胞ですが、坂口先生のノーベル賞受賞のニュースを読むと、発見に至るまでの道のりは、想像を絶するほど険しかったんですね。」
ほむほむ先生「そうなんだよ。今でこそ常識として語られているけれど、当時は本当に逆風の連続だったんだ。1970年代には『サプレッサーT細胞』っていう、免疫を抑える細胞の存在は予測されていた。でも、誰もその正体を捕まえられなくてね。」
A先生「どうして『幻』とまで言われたんですか?存在が予測されていたのに、信じてもらえなかった理由が、いまいちピンとこなくて…。」
ほむほむ先生「それはね、主に3つの大きな壁があったからなんだ。第一に、Treg細胞に特有の目印がなかったこと。第二に、実験しても研究者によって結果がバラバラで、再現性が極めて低かったこと。そして決定的だったのが、当時サプレッサー細胞の存在を支えていた『I-J遺伝子』という仮説が、後の研究で根底から覆ってしまったことなんだ[5]。土台だと思われていたものが、実は存在しなかった。これで学会全体が『サプレッサーT細胞なんて、やっぱり存在しないんじゃないか』という雰囲気に包まれて、研究自体が下火になってしまったんだ。」
A先生「うわぁ…。そんな状況で研究を続けるなんて、本当にすごい精神力ですね…。心が折れてしまいそうです。」
ほむほむ先生「本当にそうだよね。でも坂口先生は諦めなかった。『体はなぜ自分を攻撃しないのか』っていう、免疫学の根源的な謎を解きたい、その一心だったんだね。そして1980年代の初めに、マウスの実験で大きな一歩を踏み出す。生まれてすぐのマウスから胸腺という免疫の学校のような臓器を取り除くと、そのマウスが卵巣炎など、次々に自己免疫疾患を発症することを発見したんだ[6]。」
A先生「胸腺を取り除くと…!そこからどうやってTreg細胞の存在にたどり着いたんですか?」
ほむほむ先生「坂口先生はさらに実験を進めて、病気になったマウスに、健康なマウスのT細胞をごっそり移植してみたんだ[7]。『もしT細胞の中にブレーキ役がいるなら、それを補充すれば病気は治るはずだ』ってね。結果は劇的だった。正常なT細胞をもらったマウスは、自己免疫疾患を発症しなくなったんだよ。まさに、失われた『何か』を補充したら元に戻った。これで、T細胞の中に自己免疫を抑える特殊な細胞がいることが、強く示されたわけさ。」
A先生「すごい発見ですね!でも、それでもすぐには認められなかったんですよね…?」
ほむほむ先生「うん。次に、その抑制細胞が『CD25』を目印に持つことを突き止めたんだけど、さっき話したように、当時は『CD25=活性化したT細胞』というのが常識だったからね。『それは単に疲弊して動けなくなった細胞が、見かけ上、抑制しているように見えるだけじゃないか』なんて、懐疑的な声が後を絶たなかった。1995年に発表した決定的な論文も、世界的に有名なNatureやScienceといった科学雑誌からは掲載を断られてしまったんだ。」
A先生「今では信じられない話です…。悔しかったでしょうね。」
ほむほむ先生「そうだね。でも、最終的に別の免疫学の専門誌に掲載されたその論文の真価は、CD25を目印にすれば“誰でも”Treg細胞を分離できて、その抑制機能を実験で確認できるという『再現性』を明確に示したことだった[8]。ある有名な雑誌の編集者が半信半疑で部下に追試させたところ、論文通りの結果が出て、その編集者が強力な味方になってくれた、なんていう逸話も残っているくらいだよ[9]。この執念と、誰がやっても同じ結果が出るという科学的な証明が、道を切り開いたんだ。」
存在の最終証明:「Foxp3」と難病「IPEX症候群」

ChatGPTで作画
A先生「CD25の発見と再現性の証明で、Treg細胞の存在はほぼ確実になったんですね。」
ほむほむ先生「そうだね。でも、まだ最後のワンピースが足りなかった。Treg細胞を真に指揮者たらしめている本質、つまりマスターキーは何か。それが2003年に発見された、転写因子『Foxp3(フォックスピースリー)』だったんだ。坂口先生のグループを含む世界中の3つの研究グループが、ほぼ同時にこのFoxp3の重要性を突き止めたんだよ[10][11]。」
A先生「Foxp3の発見が、ついに幻を実体に変える決定打になったわけですね。」
ほむほむ先生「その通り。そして皮肉なことに、その重要性を人間において最も痛烈に証明したのが、ヒトの稀な遺伝性疾患である『IPEX症候群』という重い病気だったんだ[12]。」
A先生「Foxp3遺伝子の異常で、Treg細胞が作られない病気…でしたよね。指揮者がいないオーケストラ…。Treg細胞がいないと、一体、体はどうなってしまうんですか…?」
ほむほむ先生「生まれた瞬間から、体中の免疫がブレーキを完全に失い、全ての楽器が最大音量で不協和音を奏でるような、大暴走を始めてしまうんだ。重いアレルギー性の皮膚炎や、どうしても治らない腸炎、インスリンを作る膵臓の細胞が破壊されてしまう1型糖尿病などを次々と発症して、多くの場合、残念ながら1年以内に亡くなってしまう、非常に過酷な病気なんだ。」
A先生「そんな…。でも、その病気の存在が、Treg細胞という指揮者が私たち人間にとっていかに不可欠な存在であるかを、誰にも否定できない形で証明したんですね。」
ほむほむ先生「うん…。悲しいことだけど、その通りなんだ。このIPEX症候群という病気とFoxp3遺伝子の異常が結びついたことで、Treg細胞がヒトの免疫系の正常な維持、特に自分を攻撃しない『自己寛容』に絶対必要だということが、疑いようもなく証明された。幻の細胞を巡る長い論争に、終止符が打たれた瞬間だったんだよ。」
多彩な指揮術! Treg細胞はどうやって免疫を抑えるのか

ChatGPTで作画
A先生「では、そのTreg細胞は、具体的にはどんなテクニックでオーケストラを指揮しているんでしょうか?」
ほむほむ先生「Treg細胞は、実に多彩な手を使うんだ。まるで熟練の指揮者のようにね。主な戦略は大きく3つあるよ。一つ目は『兵糧攻め』だ。他のT細胞が増殖するのに必要な『IL-2(インターロイキン-2)』という栄養ドリンクのような物質を、Treg細胞自身が先回りしてごくごくと飲み干してしまう。これで、暴走しそうな攻撃役のT細胞はエネルギー不足に陥り、アポトーシスという細胞の自死に至るんだ[13]。」
A先生「なるほど、相手のエネルギー源を断ってしまうんですね。直接的ではないけれど、すごく効果的ですね!」
ほむほむ先生「二つ目は『鎮静シグナル』。今度は『IL-10』や『TGF-β』といった、周りの免疫細胞を落ち着かせるメッセージ物質(サイトカイン)を周りに放出するんだ[14]。これらの物質は、興奮して音を大きくしすぎている奏者たちに『まあまあ落ち着いて、ここは静かに演奏するパートだよ』という信号を送り、炎症という名の不協和音をクールダウンさせてくれる。」
A先生「平和を呼びかける伝令役みたいですね。優しい指揮法ですね。」
ほむほむ先生「そして三つ目は、もっと直接的な『直接指導』だよ。Treg細胞の表面にある『CTLA-4』という分子を使って、免疫の司令塔になる細胞(抗原提示細胞)の表面にあるアクセル装置(CD80/CD86)を、物理的に奪い取ってしまうんだ[15]。『君の楽器は一旦預かるよ!』と取り上げてしまうようなものだね。これらの戦略を、状況に応じて巧みに使い分けていると考えられているよ。」
A先生「兵糧攻めに、鎮静シグナル、そして直接指導…。想像以上に多様な方法で、免疫のハーモニーを守っているんですね。」
バランスが全て! Treg細胞と病気の深い関係

ChatGPTで作画
A先生「Treg細胞が免疫のバランスを保つ上で、本当に重要な役割を果たしていることがよく分かりました。ということは、このバランスが崩れると…」
ほむほむ先生「その通り。様々な病気に繋がってしまうんだ。例えば、Treg細胞が少なすぎたり、働きが悪くなったりして指揮が甘くなると、ブレーキが効かなくなる。その結果、関節リウマチや1型糖尿病などの『自己免疫疾患』や、A先生が診ていたようなアトピー性皮膚炎、食物アレルギーといった『アレルギー性疾患』のリスクが高まるんだ。」
A先生「では逆に、Treg細胞が多すぎて、指揮が厳しすぎるとどうなるんですか?」
ほむほむ先生「いい質問だね、A先生。ブレーキが効きすぎると、今度はどうなると思う?」
A先生「えっと…本来、力強く演奏しなければならない場面で、みんなが小さな音しか出せなくなってしまう…。つまり、やっつけなければならない悪いやつら、例えばウイルスとか、がん細胞とかを見逃してしまう…ということでしょうか?」
ほむほむ先生「その通り!まさに、冒頭で僕が言った『指揮者が、時に招かれざる客のために演奏を指揮してしまう』という状況が生まれる。Treg細胞が多すぎたり働きすぎたりすると、本来やっつけなければならない病原体に対する免疫や、がん細胞を見つけて排除する『免疫監視』の機能が弱まってしまう可能性があるんだ[16]。その結果、感染症にかかりやすくなったり、がん細胞が増えるのを許してしまったりする。実は、多くのがん組織の中にはTreg細胞が多数集まってきていて、がんを攻撃しようとするキラーT細胞に強力なブレーキをかけている。まるで、がん細胞がTreg細胞を味方につけて、『私たちを攻撃しないで』と指揮させているような状態なんだ。その結果、がんの増殖や転移を手助けしてしまっている。だからこそ、最近のがん免疫療法では、このTreg細胞のブレーキをいかにして外すかという戦略が、非常に重要になっているんだよ[17]。」
A先生「そういうことだったんですね…。Treg細胞は絶対的な善玉というわけではなく、そのバランスこそが重要なんだ…。」
未来の医療を拓く! Treg細胞を用いた最新治療法

ChatGPTで作画
A先生「Treg細胞の働きがこんなに詳しく分かってきたということは、それを応用した新しい治療法の研究も進んでいるんですね!」
ほむほむ先生「うん、世界中で物凄い勢いで進められているよ。特に自己免疫疾患やアレルギー、臓器移植後の拒絶反応に対する治療として大きな期待が寄せられている。例えば、患者さん自身の血液からTreg細胞を取り出して、体の外で安全に増やしてから体内に戻す『Treg細胞療法』は、すでに臨床試験が進んでいるんだ。」
A先生「自分の細胞を使うので、体への負担も少なそうで、すごく希望が持てますね。」
ほむほむ先生「そうだね。ただ、道は平坦ではないんだ。実はごく最近、2024年に発表されたアメリカでの研究では、発症したばかりの小児の1型糖尿病の患者さんに、このTreg細胞療法を行ったんだ[18]。結果として、残念ながら期待されていたほどの効果、つまり自分のインスリンを出す力を維持する効果は、はっきりと示されなかった。でもね、これは失敗ではなくて、非常に重要な一歩なんだ。どのくらいの量のTreg細胞を、どのタイミングで、どうやって戻せば最も効果的なのか。そうした課題を示した、次につながる貴重なデータなんだよ。」
A先生「そうなんですね…。すぐに結果が出なくても、着実に前に進んでいるんですね。」
ほむほむ先生「その通り。さらに賢い方法も考えられていて、特定の病気の原因となっている標的だけをピンポイントで攻撃できるように、Treg細胞にGPSを搭載するような遺伝子操作をする技術も開発されているんだ。特定の標的だけを狙い撃ちするブレーキ、『CAR-Treg療法』なんて呼ばれているよ[19]。「CAR-T細胞療法」に関しては、以前も解説したよね[20]」
A先生「まさに『狙い撃ちするブレーキ』ですね!がん治療では、その全く逆のアプローチになるわけですね。Treg細胞が、こんなにも医療の希望になるなんて…。今日はありがとうございました。目の前が開けたような気持ちです!」
ほむほむ先生「そう言ってもらえて嬉しいよ。Treg細胞の研究は、iPS細胞から必要な機能を持ったTreg細胞をオーダーメイドで大量に作り出す研究にも繋がっている。これが実現すれば、今まで治療が難しかった多くの難病に立ち向かう、新しい武器になるかもしれない。A先生のように若い医師がこの分野に強い興味を持ってくれることこそが、未来の医療を創っていく原動力なんだよ。」
まとめ

筆者作成
✅ Treg細胞は、免疫というオーケストラの“冷静沈着な指揮者”です。
私たちの体内で免疫細胞が過剰に反応したり、自分自身を攻撃したりしないように監視し、絶妙なタイミングでタクトを振る重要な役割を担っています。このTreg細胞のおかげで、私たちの体内の免疫の精緻なハーモニーは維持されています。その発見は、日本人研究者の不屈の探求心の末に成し遂げられた、医学史におけるドラマなのです。
✅ Treg細胞のバランスの乱れが、様々な病気の引き金になります。
Treg細胞という指揮者が弱まると免疫は暴走し、自己免疫疾患やアレルギーのリスクが高まります。一方で、指揮が厳しすぎると、今度は感染症への抵抗力が弱まったり、がん細胞という招かれざる客の増殖を許してしまったりする可能性があります。健康は、この免疫のアクセルとブレーキの精緻なバランスの上に成り立っているのです。
✅ Treg細胞を応用した治療法は、未来の医療に大きな希望をもたらします。
Treg細胞を「増やして」自己免疫疾患を治療する試みや、逆にがん組織で働くTreg細胞を「減らして」がんへの攻撃力を高める治療法など、その応用研究が世界中で進んでいます。臨床試験では課題も見つかっていますが、それら一つ一つが未来への確実なステップとなっています。将来的には、遺伝子改変技術などと組み合わせ、難病に対するオーダーメイドの細胞療法が実現するかもしれません。
参考文献
[2] Raskov H, Orhan A, Christensen JP, Gögenur I. Cytotoxic CD8+ T cells in cancer and cancer immunotherapy. British Journal of Cancer 2021; 124:359-67.
CD8⁺細胞傷害性T細胞の生物学(分化、抗原認識、免疫シナプス、殺傷分子)を丁寧に概説したうえで、腫瘍微小環境(免疫抑制、代謝的制約、免疫チェックポイント)による機能障害(exhaustion)のメカニズムを整理する。
[3] Sakaguchi S, Sakaguchi N, Asano M, Itoh M, Toda M. Immunologic self-tolerance maintained by activated T cells expressing IL-2 receptor alpha-chains (CD25). Breakdown of a single mechanism of self-tolerance causes various autoimmune diseases. J Immunol. 1995 Aug 1;155(3):1151-64. PMID: 7636184.
CD4⁺CD25⁺細胞は抗原非特異的に免疫応答の活性化段階を抑え、末梢の自己寛容を維持する重要な制御機能を持つと示され、このメカニズムの破綻が自己免疫疾患の一因になりうることを示した。後の「制御性T細胞(Treg)」研究の基礎を築いた古典的報告。
[4] Sakaguchi S, Yamaguchi T, Nomura T, Ono M. Regulatory T cells and immune tolerance. Cell. 2008 May 30;133(5):775-87. doi: 10.1016/j.cell.2008.05.009. PMID: 18510923.
坂口先生らの総説で、Treg(制御性T細胞)の生物学と自己免疫抑制における役割を体系的にまとめています。本総説は、CD4⁺CD25⁺で見つかった従来の表面マーカーに加え、核内転写因子であるFoxp3がTregの“系統を決める”重要因子であることを解説している。
[5] Workman CJ, Szymczak-Workman AL, Collison LW, Pillai MR, Vignali DA. The development and function of regulatory T cells. Cell Mol Life Sci. 2009 Aug;66(16):2603-22. doi: 10.1007/s00018-009-0026-2. Epub 2009 Apr 24. PMID: 19390784; PMCID: PMC2715449.
サプレッサーT細胞に対し明確な細胞表面マーカーや遺伝子マーカーが無く、「抑制」現象の原因が同定しづらかったこと、実験系(細胞移入、混合培養など)に依存する部分が大きく、研究グループ間で再現性が低かったこと、マウス免疫遺伝学で報告された「I-J 遺伝子領域(抑制因子に関与するとされた)」の実体が見つからず、その仮説が崩れたことが大きな打撃となり、 “サプレッサー”概念は科学界で長く疑問視され、分野としての停滞も起きたことを解説。
[6] Sakaguchi S, Takahashi T, Nishizuka Y. Study on cellular events in postthymectomy autoimmune oophoritis in mice. I. Requirement of Lyt-1 effector cells for oocytes damage after adoptive transfer. J Exp Med. 1982 Dec 1;156(6):1565-76. doi: 10.1084/jem.156.6.1565. PMID: 6983557; PMCID: PMC2186857.
1980年代初め、坂口志文らは「出生直後のマウスから胸腺を除去」すると、そのマウスが卵巣炎などの臓器特異的自己免疫を起こすことを示した。これは「新生児期に胸腺由来のあるT細胞群が自己寛容を保つのに必須である」ことを示唆する重要な観察だった。
[7] Sakaguchi S, Takahashi T, Nishizuka Y. Study on cellular events in postthymectomy autoimmune oophoritis in mice. I. Requirement of Lyt-1 effector cells for oocytes damage after adoptive transfer. J Exp Med. 1982 Dec 1;156(6):1565-76. doi: 10.1084/jem.156.6.1565. PMID: 6983557; PMCID: PMC2186857.
正常マウスからの脾細胞/胸腺細胞を移入するとその自己免疫を防げること、移入で防げる細胞群が当時の標識でいうLyt-1(現在のCD4に相当)に富むことを示した。これにより「抑制(suppressor/regulatory)機能を持つ成熟T細胞が存在するはずだ」という考えが強まった。
[8] Sakaguchi S, Sakaguchi N, Asano M, Itoh M, Toda M. Immunologic self-tolerance maintained by activated T cells expressing IL-2 receptor alpha-chains (CD25). Breakdown of a single mechanism of self-tolerance causes various autoimmune diseases. J Immunol. 1995 Aug 1;155(3):1151-64. PMID: 7636184.
坂口らは「末梢で自己反応を抑えるCD4⁺CD25⁺のT細胞(いわゆる自然免疫調節性T細胞、Treg)」を同定・機能的に示した。これが現在の「制御性T細胞(regulatory T cell, Treg)」概念確立の大きな一歩となった。
[9]制御性T細胞とがん微小環境 【細胞の発見と免疫寛容】 《Part.1》
[10] Ramsdell F. Foxp3 and Natural Regulatory T Cells: Key to a Cell Lineage? Immunity 2003; 19:165-8.
[11] Sakaguchi S, Ono M, Setoguchi R, Yagi H, Hori S, Fehervari Z, Shimizu J, Takahashi T, Nomura T. Foxp3+ CD25+ CD4+ natural regulatory T cells in dominant self-tolerance and autoimmune disease. Immunol Rev. 2006 Aug;212:8-27. doi: 10.1111/j.0105-2896.2006.00427.x. PMID: 16903903.
2000年代以降、FoxP3という転写因子がTregの本質的マーカー/機能因子であることが見いだされ(FoxP3変異はマウスや人の重篤な自己免疫疾患につながる)、Treg研究は免疫寛容と自己免疫の理解に決定的な影響を与えた。坂口先生の一連の業績はその歴史的基点とされている。
[12] Bennett CL, Christie J, Ramsdell F, Brunkow ME, Ferguson PJ, Whitesell L, et al. The immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked syndrome (IPEX) is caused by mutations of FOXP3. Nature Genetics 2001; 27:20-1.
IPEX患者で FOXP3 遺伝子に異常(複数の変異)があることを報告。これにより、マウスの scurfy 表現型(Foxp3 欠損)で見られる重度の自己免疫と対応するヒト疾患が、同じ転写因子の欠陥で起きることが示された。ヒトでも FOXP3 が免疫寛容(=自己攻撃を抑える)に不可欠である直接的な遺伝学的証拠となった。
[13] Pandiyan P, Zheng L, Ishihara S, Reed J, Lenardo MJ. CD4+CD25+Foxp3+ regulatory T cells induce cytokine deprivation–mediated apoptosis of effector CD4+ T cells. Nature Immunology 2007; 8:1353-62.
マウスや共培養実験で、Foxp3⁺ Treg が周囲の IL-2 を減らし、IL-2 欠乏によりエフェクターCD4⁺T 細胞がBim依存的にアポトーシスを起こすことを示した。これが「サイトカイン飢餓(cytokine-deprivation)による抑制」メカニズム。
[14] Groux H, O'Garra A, Bigler M, Rouleau M, Antonenko S, de Vries JE, Roncarolo MG. A CD4+ T-cell subset inhibits antigen-specific T-cell responses and prevents colitis. Nature. 1997 Oct 16;389(6652):737-42. doi: 10.1038/39614. PMID: 9338786.
慢性刺激下にIL-10を加えた条件で得られるCD4+クローン(Tr1と命名)は高IL-10産生・低増殖性で、標的T細胞応答を抑制しコロイティスを防いだ。これは“IL-10が誘導する抑制性CD4+サブセット(Tr1)”を示す代表的な報告で、IL-10の“能動的な免疫抑制作用”を示した古典的研究。
[15] Qureshi OS, Zheng Y, Nakamura K, Attridge K, Manzotti C, Schmidt EM, Baker J, Jeffery LE, Kaur S, Briggs Z, Hou TZ, Futter CE, Anderson G, Walker LS, Sansom DM. Trans-endocytosis of CD80 and CD86: a molecular basis for the cell-extrinsic function of CTLA-4. Science. 2011 Apr 29;332(6029):600-3. doi: 10.1126/science.1202947. Epub 2011 Apr 7. PMID: 21474713; PMCID: PMC3198051.
CTLA-4が相手細胞からCD80/CD86を取り込む(trans-endocytosis)ことを実験で示し、CTLA-4の細胞外的(cell-extrinsic)な抑制機構を提案。
[16] Shang B, Liu Y, Jiang S-j, Liu Y. Prognostic value of tumor-infiltrating FoxP3+ regulatory T cells in cancers: a systematic review and meta-analysis. Scientific Reports 2015; 5:15179.
多くのがん種を対象としたメタ解析で、腫瘍中に多く浸潤するFOXP3陽性Tregは、がん種による差はあるものの、乳がんやメラノーマなどでは再発率の上昇や生存率低下と有意に関連していた。つまり腫瘍微小環境でのTreg過剰が腫瘍免疫を抑え、悪化に寄与することを大規模データで支持する。
[17] Shan F, Somasundaram A, Bruno TC, Workman CJ, Vignali DAA. Therapeutic targeting of regulatory T cells in cancer. Trends Cancer. 2022 Nov;8(11):944-961. doi: 10.1016/j.trecan.2022.06.008. Epub 2022 Jul 16. PMID: 35853825; PMCID: PMC9588644.
腫瘍内Tregは多重の抑制機構(接触依存性の細胞傷害、免疫抑制性サイトカイン、代謝的制御など)でエフェクターT細胞を抑え、しばしば予後不良に寄与する。レビューはTregの動員・安定化メカニズムを整理し、CTLA-4/IL-2経路や表面マーカーを標的にした抗体・免疫毒(immunotoxin)、選択的代謝阻害などの戦略を概観。
[18] Bender C, Wiedeman AE, Hu A, Ylescupidez A, Sietsema WK, Herold KC, Griffin KJ, Gitelman SE, Long SA; T-Rex Study Group†; T-Rex Clinical Study Group. A phase 2 randomized trial with autologous polyclonal expanded regulatory T cells in children with new-onset type 1 diabetes. Sci Transl Med. 2024 May 8;16(746):eadn2404. doi: 10.1126/scitranslmed.adn2404. Epub 2024 May 8. PMID: 38718135.
小児の新規発症1型糖尿病を対象に自家由来ex vivo拡大polyclonal Tregの単回投与を用いた二重盲検ランダム化第II相。主要所見は「安全性は維持されたが、1年でのC-ペプチド(残存β細胞機能)低下を防ぐ有意差は認められなかった」というものだった
[19] Arjomandnejad M, Kopec AL, Keeler AM. CAR-T Regulatory (CAR-Treg) Cells: Engineering and Applications. Biomedicines. 2022 Jan 26;10(2):287. doi: 10.3390/biomedicines10020287. PMID: 35203496; PMCID: PMC8869296.
CAR-Tregの技術的背景、適応領域(移植、自己免疫、遺伝子治療におけるAAV免疫制御等)、利点と課題(標的指向性の向上、Tregの安定性・疲弊・コスト)が体系的にまとまった総説。
[20] 小児白血病に使用される「キムリア」とは?高額でも重要な治療方法と開発史を、小児科医がわかり易く解説
https://pedsallergy.theletter.jp/posts/8c4a6940-f203-11ef-8333-bb82b948d13b
すでに登録済みの方は こちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績