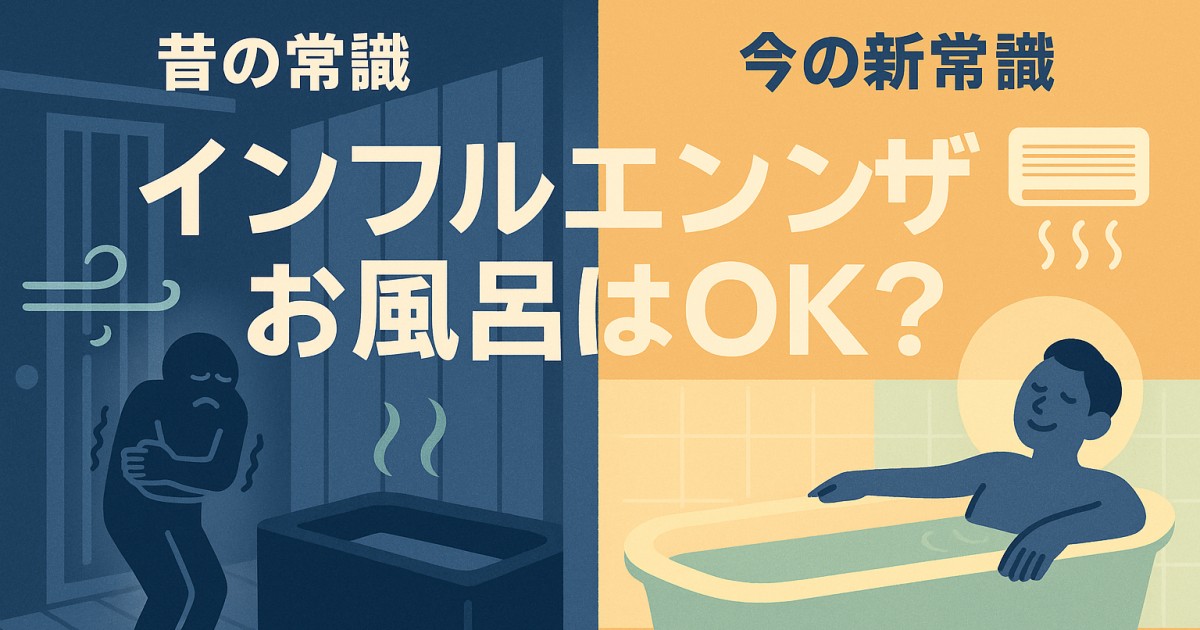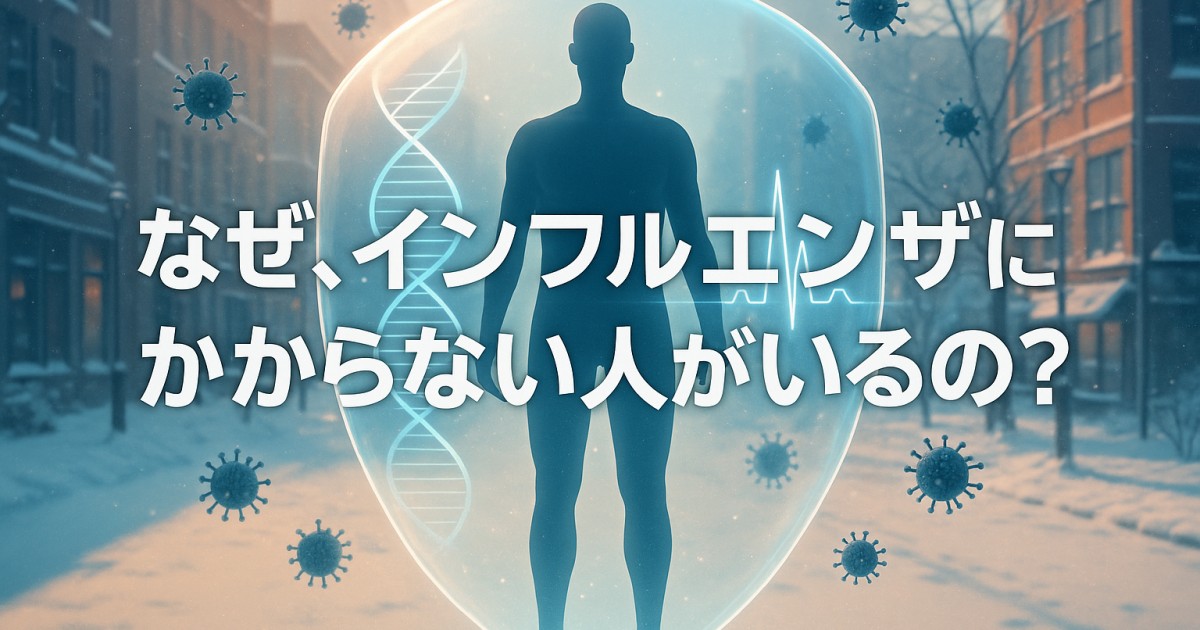子どもとカフェインの知っておきたい影響とは?
コーヒーや紅茶、エナジードリンクに含まれるカフェインが子どもに与える影響について質問されることがあります。特に「何歳くらいからなら大丈夫なのか」と尋ねられることは少なくありません。
今回は、ほむほむ先生とA先生の会話形式で、カフェインに関して深堀りしていきます。
A先生「先生、最近、外来でカフェインについて聞かれることがあったんです。特に、小学生のお子さんを持つお母さんから、『エナジードリンクって、テスト勉強の時に飲ませても大丈夫なんでしょうか?』なんて聞かれたりして…正直、ドキッとしちゃいました。」
ほむほむ先生「ああ、それはタイムリーな話題ですね、A先生。確かに、子ども向けのカラフルなパッケージのものも増えましたし、親御さんも気になるところでしょう。じゃあ今日はそのカフェインについて、掘り下げてみましょうか。A先生も、日々の診療で役立つ知識が得られると思いますよ。」
A先生「よろしくお願いします!」
この記事を最後まで読めば、きっとあなたも…
-
カフェインって一体何者? その意外な歴史とは?
-
どうして子どもはカフェインにデリケートなの?
-
子どもへのカフェイン、具体的にどんな影響があるの?
-
結局、何歳くらいからなら大丈夫なの?
こんな疑問が解消するはずです。
カフェインって何?~コーヒー豆から文豪ゲーテまで、意外なつながり~

ChatGPTで作画
ほむほむ先生「さてA先生、そもそもカフェインって、どんな物質かご存知ですか?」
A先生「コーヒー豆とかお茶の葉、あとカカオなんかに入っている成分ですよね。眠気覚ましにコーヒーを飲む、みたいなイメージが強いです。」
ほむほむ先生「その通り。カフェインはね、そういう植物たちの中に自然に存在する『アルカロイド』っていう有機化合物の一種なんです[1]。」
A先生「アルカロイド…ですか。うーん、言葉は聞いたことあるんですが、具体的にはどんなものなんでしょう? 植物由来の、何か体に作用する成分、くらいのイメージで合っていますか?」
ほむほむ先生「その通りです。A先生。もっと身近なもので例えるなら、唐辛子の辛味成分カプサイシンや、じゃがいもの芽に含まれるソラニンなんかもアルカロイドの仲間なんですよ。それぞれ植物が自分を守るためだったり、何かしらの役割を持って作り出す化学物質の総称、みたいなイメージですね。そして、このカフェインは、世界で最も広く親しまれている精神刺激薬、つまり脳を興奮させる作用がある物質、と言えるんです。私たちの脳の中にはね、『アデノシン』という、そろそろ休もうねと眠気を誘う、いわばブレーキ役の物質があるんですが…[2]。」
A先生「アデノシン!名前はよく聞きます。なんだか、こう、体が『もう疲れたよ~』ってサインを出してる感じですかね?」
ほむほむ先生「まさにそんな感じです。で、カフェインは、そのアデノシンがくっつくべき場所、専門的には『受容体』って言うんだけど、そこにアデノシンより先にピタッとくっついてブロックしちゃうんです。」
A先生「へえー!まるで、アデノシンっていう『おやすみ係』が席に着こうとしたら、カフェインが椅子取りゲームみたいにサッと席を取っちゃう、みたいな感じですね!」
ほむほむ先生「まさにそんな感じです。だから、おやすみ係は仕事ができなくて、脳が『まだ活動時間だ!』と勘違いしてしまうわけですね。その結果、目が覚めたり、一時的に集中力がアップしたりする、というわけです。」
A先生「なるほど。だからコーヒーを飲むと、頭がシャキッとするんですね!納得です。他にも何か作用はあるんですか?」
ほむほむ先生「ええ、他にも心臓の拍動を少し速めたり、胃酸の分泌を促したりする作用もあるんですよ。」
A先生「なるほど、結構いろいろ働くんですね。ところで先生、このカフェインって、いつ頃発見されたものなんですか?」
ほむほむ先生「カフェインそのものが発見されたのは1819年。ドイツのフリードリープ・フェルディナント・ルンゲという化学者によるものなんです。そしてね、ここからがちょっと面白い話なんですが、彼にコーヒー豆の分析を依頼したのが、なんと、あの文豪ゲーテだったと言われているんですよ[3]。」
A先生「ええっ!?『若きウェルテルの悩み』とか『ファウスト』の、あのゲーテですか!?なんだか、文学と科学が意外なところで繋がっていて、すごく面白いですね!コーヒー好きが高じて、科学的な探求心まで刺激されちゃったんでしょうか。」
ほむほむ先生「そうみたいですね。ゲーテ自身も大変なコーヒー愛飲家で、その不思議な覚醒効果の源泉に、強い興味を抱いていたようです。文豪の日常と科学の発見が交差するなんて、なんだかロマンがありますよね。」
A先生「いやー、びっくりしました。カフェインの正体から、まさかゲーテの名前が出てくるなんて、思ってもみませんでした!」
『ほむほむ先生の医学通信』では、様々な学会で委員を務め25年以上の臨床経験を持つ小児科医が、医学知識をわかりやすく解説します。無料登録で定期的に記事をお読みいただけるほか、サポートメンバーにご登録いただくと過去の記事アーカイブすべてにアクセスできます。皆様のサポートは子どもたちの健康に関する研究継続に役立てられております。よろしければご登録をご検討ください。※この記事はサポートメンバー限定です。
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績