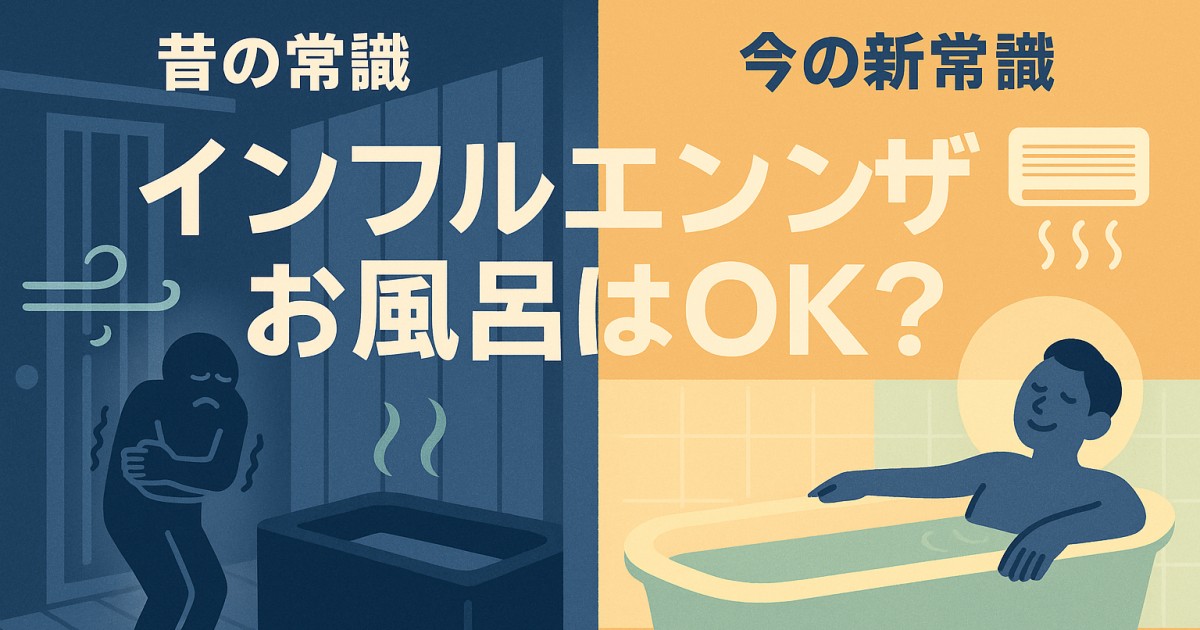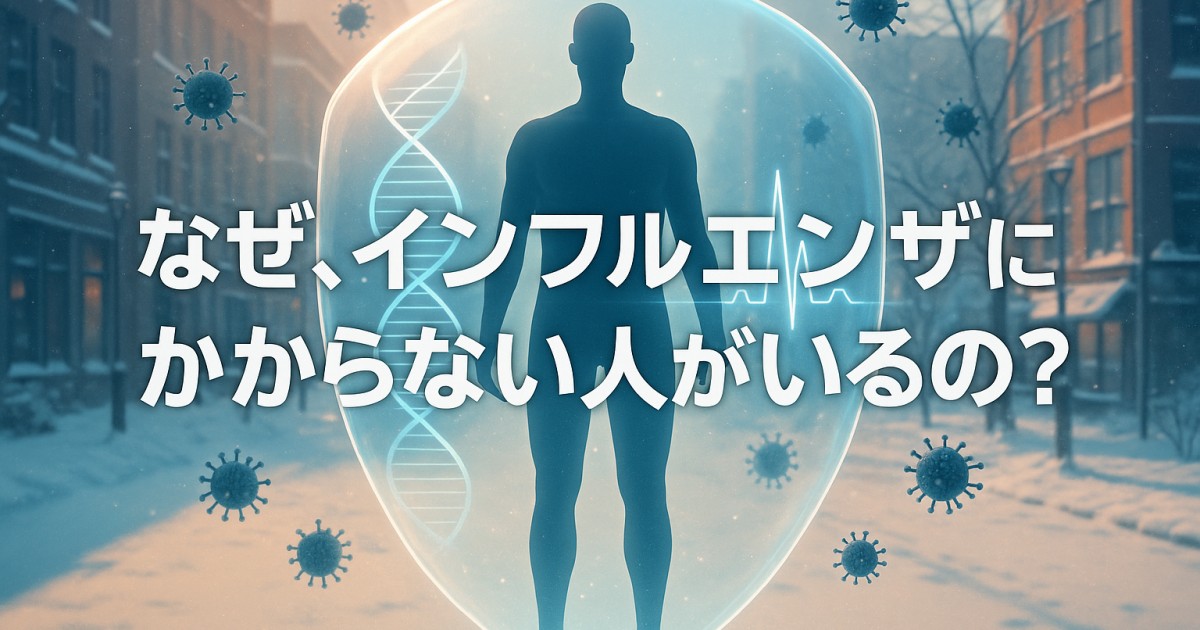「二酸化炭素濃度が高いとあくびが出る」説はもう古い?
私たちは日常的にあくびを経験しますが、その背後には、単なる眠気だけでは説明できない、さまざまな生理的・心理的な要因が隠されていることがあります。そもそも、「二酸化炭素を追い出すため…」というのは古い説のようです。
そこで今回は、ほむほむ先生とAさんの会話を通じて、あくびの基本的な定義から、睡眠不足との深い関係、そして見過ごされがちな他の医学的な原因に至るまで、科学的な知見に基づいて掘り下げていきます。この記事を読めば、あくびに対する理解が深まり、ご自身の体調を見つめ直すきっかけになるかもしれません。
本記事を最後まで読めば、
・あくびの本当の理由は?
・睡眠不足とあくびの関係は?
・あくびの他の原因とは?
これらの疑問にお答えできるよう執筆しました。
研修医Aさん(以下Aさん)「(あくびをしているほむほむ先生をみて)先生、眠そうですね。」
ほむほむ先生「最近、論文や夜間救急で寝不足だったからかなあ」
Aさん「やっぱり、あくびって寝不足だからでるんでしょうかね。二酸化炭素を追い出すため…なんていう説を見たことがあるような。」
ほむほむ先生「なるほど、では『頻繁なあくびは睡眠不足のサインなのか』っていうテーマで考えてみますか?」
Aさん「いきなりですか(笑)。まあはい、よろしくお願いいたします。」
あくびの定義と俗説、「脳に酸素を送るため?」

ChatGPTで作画
ほむほむ先生「早速ですが、Aさんはあくびについて、どのようなイメージをお持ちですか?」
Aさん「ええ、そうですね。ただ口を大きく開けて息をするだけではないですね。単純な現象ではないとは思います。」
ほむほむ先生「あくびは『口を大きく開けながらゆっくり深く息を吸い込み、その後短く息を吐き出す、一連の独特な動作』といえます[1]。人から人へとうつる『伝染性のあくび』という現象も知られていますね。」
Aさん「はい、伝染性のあくびは経験があります。一般的には、あくびは眠い時や退屈している時に出るサインだと思われがちですよね。」
ほむほむ先生「ええ、そうですね。しかし、実はもう少し複雑なメカニズムが関わっている可能性があるのです。例えば、以前よく言われていた『脳の酸素が不足しているため、あくびで酸素を補給する』という説がありましたが、ご存じですか?」
Aさん「はい、聞いたことがあります。それが本当の理由なのでしょうか?」
ほむほむ先生「ある実験では、空気中の酸素濃度や二酸化炭素濃度を変化させても、あくびの頻度には変わりがなかったという結果が報告されています[2]。」
Aさん「へえ、そうだったのですね。では、その説はあまり有力ではないということですか。」
ほむほむ先生「はい、現在ではそのように考えられているみたいですね。」
『ほむほむ先生の医学通信』では、様々な学会で委員を務め25年以上の臨床経験を持つ小児科医が、医学知識をわかりやすく解説します。無料登録で定期的に記事をお読みいただけるほか、サポートメンバーにご登録いただくと過去の記事アーカイブすべてにアクセスできます。皆様のサポートは子どもたちの健康に関する研究継続に役立てられております。よろしければご登録をご検討ください。 この記事は登録後、全文無料で閲覧可能です。
この記事は無料で続きを読めます
- あくびの意外な役割と脳の冷却
- 頻繁なあくびと睡眠不足やはり関連あり?
- 睡眠不足以外のあくびの原因病気のサインも
- 子どものあくび大人とは違う視点
- まとめ
- 参考文献
すでに登録された方はこちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績