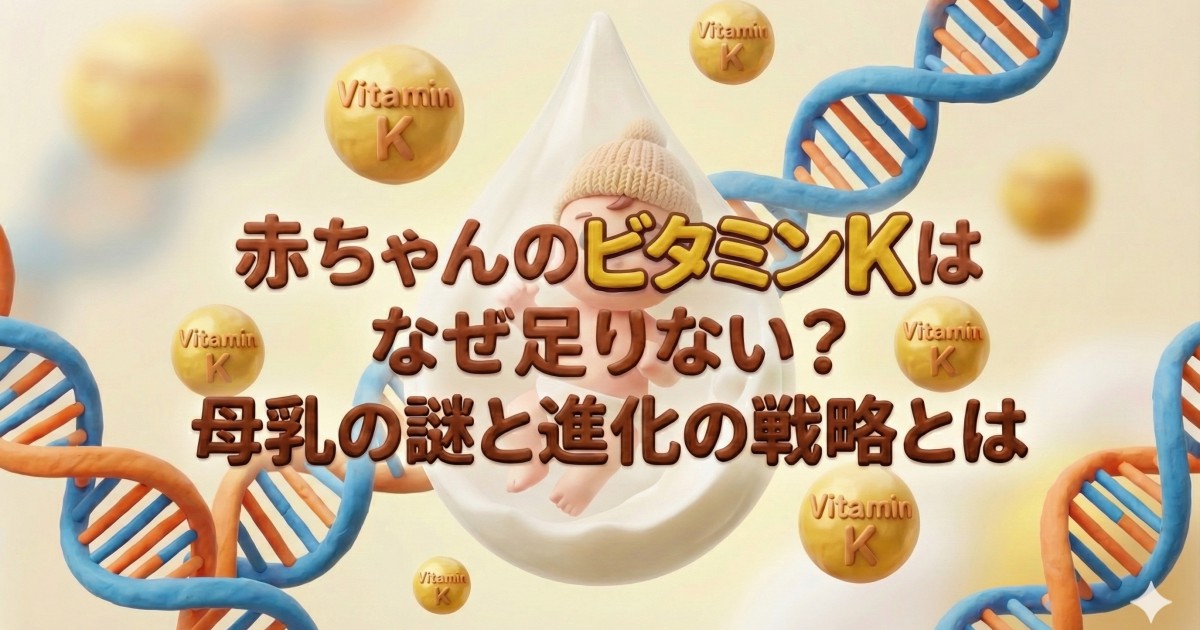予防接種、ためらう心と「変われない」信念の違いとは
小児科専門医のほむほむ先生のもとで日々研鑽を積む研修医A先生。ある日、外来で赤ちゃんの予防接種スケジュールについて説明していた時のこと。熱心にメモを取る母親の隣で、父親がポツリと「本当に全部打たないといけないのかなぁ…ネットで色々見ると、なんだか不安で…」と呟いたのが耳に残っていました。
A先生「ほむほむ先生、今日もお疲れさまです。ちょっとご相談したいことがあるのですが…今日の外来で、あるお父さんがすごく不安そうな顔をされていたんです。最近、ネットニュースやSNSでも、ワクチンに関する様々な意見を目にする機会が増えて、改めて思ったのですが…ワクチンに対する考え方って、どうしてこんなにも人によって違うのでしょうか?それに、一度『こうだ』と信じ込んだ考えを、後から変えるのって、どうしてあんなに難しいんでしょうか?」
ほむほむ先生「A先生、お疲れさま。それは、日々患者さんと接する中で、大切な視点だと思いますよ。では、今日はその『ワクチンへのためらい』、すなわちワクチンヘジテンシーと、もう一つ、『反ワクチン』と呼ばれる立場、そして、特に公の立場にある人が一度示した意見をなかなか変えられない背景について、一緒に考えてみましょうか。」
本記事を最後まで読めば、
・「ワクチンへのためらい(ワクチンヘジテンシー)」と「反ワクチン」はどう違う?
・有名人が反ワクチン的な意見を変えにくいのはなぜ?
・一度信じた考え方を変えることは可能なの?
これらの疑問にお答えできるよう執筆しました。
ワクチンへの「ためらい」と「反ワクチン」、その違いとは?

ChatGPTで作画
ほむほむ先生「さて、A先生。まずは基本から押さえていきましょうか。大切なこととして、ワクチンへのためらい、専門的には『ワクチンヘジテンシー(vaccine hesitancy)』と言うのだけれど、これと、いわゆる『反ワクチン』とは、区別して考える必要があるんですね[1]。」
A先生「ヘジテンシー…ですか。これまで漠然と『ワクチンに積極的じゃない人』くらいにしか捉えていませんでした。その二つ、具体的にはどんな違いがあるんでしょうか?」
ほむほむ先生「まず、『ワクチンヘジテンシー』というのは、言葉の通り、ワクチン接種を『ためらう』気持ちのことなんです。例えば、ワクチンの安全性や効果について、まだ十分に納得できていなかったり、情報が足りなくて判断に迷っていたりする状態を指すんですね[1]。ですから、こうした方々とは、じっくり対話したり、正確な情報を提供したりすることで、考えが変わる可能性は十分にあると思いますよ。むしろ、疑問を持つこと自体は、情報を吟味しようとする健全な反応とも言えるかもしれませんね。」
A先生「なるほど! 先ほどの外来のお父さんも、もしかしたらこの『ヘジテンシー』の状態だったのかもしれませんね…。情報を求めているけれど、何を信じたらいいか分からなくて不安、みたいな。確かに、そういう方であれば、私たち医療者が丁寧に説明することで、安心していただける可能性はありそうです。」
ほむほむ先生「その通りです。A先生が感じたように、対話の余地があるのがヘジテンシーの特徴といえます。一方で、『反ワクチン』となると、少し様相が異なってくるんですね。こちらは、ワクチンそのものに対して、もっと根本的で、確固たる反対の立場を取っている場合が多いようなんです。単なる疑問というよりは、固定化された信念、時にはイデオロギー的な背景(特定の思想や信条に基づく考え方)が関係していると考えられているんですよ[2]。」
A先生「イデオロギー…ですか。そうなると、単に情報提供するだけでは、なかなか難しいかもしれませんね。ヘジテンシーと反ワクチン、この二つをしっかり区別して理解することが、私たち医療者にとっても、適切なコミュニケーションの第一歩になりそうですね。」
公人の立場と信念:ロバート・F・ケネディ・ジュニア氏の事例から考える

ChatGPTで作画
ほむほむ先生「その通りですね。そして、もう一つ踏み込んで考えてみたいのが、ロバート・F・ケネディ・ジュニア氏のような、社会的に影響力のある人物が、一度公に示した反ワクチンとも取れるような考えを、なぜなかなか変えられないのか、という点ですね。」
A先生「ロバート・F・ケネディ・ジュニア氏…。ニュースでもよく見かけしますよね。ご本人は『反ワクチンではない』と主張されているようですが[3]、その言動には、正直ちょっと矛盾しているように感じてしまう部分もあります。例えば、麻疹が流行した時には、MMRワクチンを支持するような発言をされたこともあったと記憶していますが…[4]。あれは一体どういうことだったんでしょう?」
ほむほむ先生「よく見ていますね、A先生。確かに、そうした発言は大きな注目を集めたんですよ。ただ、あれをもって彼の根本的なスタンスが変化したと断言するには、まだ材料が乏しいというのが現状ではないでしょうか[4]。実際、その発言は彼の支持者から強い反発を招いたと報道されていますし[5]、同時に、科学的根拠が疑わしい代替療法も推奨し続けている側面があるんです。例えば、最近も彼が『タラの肝臓オイル(ビタミンAとDを含む)が麻疹対策として有望だ』といった発言を繰り返した結果、それを信じた一部の保護者がワクチンではなくサプリメントを選び、ワクチン未接種のお子さんが大量のビタミンAを摂取してしまい、肝機能障害などを起こす急性ビタミンA中毒の症例が急増した、という報道もありましたね[6][7]。」
A先生「えっ、そうなんですか!? ビタミンAで麻疹対策というのは、医学的に推奨されていることなんですか? それで健康被害が出てしまうなんて…大変なことです。あの発言は、てっきり考えを改めたシグナルなのかと思っていましたが、そういった代替療法を推奨しているとなると、やはり一貫性がないように感じてしまいます。支持者の反応も影響するとなると、本当に単純な話ではないんですね。なんだか、がんじがらめになっているような…。」
ほむほむ先生「その通りですね。WHO(世界保健機関)や米国小児科学会は、麻疹に罹患した子どもに対して、合併症のリスクを減らす目的で、医療監督下でのビタミンA投与を推奨していますが、それはあくまで治療の補助であって、麻疹の予防や、日常的な大量摂取を推奨するものでは全くないんです[8]。
それなのに、影響力のある人物の発言がきっかけで、実際に健康被害が起きてしまうというのは残念なことです。まさに、一度確立した公的なイメージや支持基盤を覆すのは、その人にとって大きなリスクを伴うんですね。彼のケースは、公的な人物が一度そういった立場を取ってしまうと、そこから離れるのがいかに難しいかを示していると言えるでしょう。」
A先生「うーん、そう考えると、単に『事実と違うから考えを変えます』とは言えない、もっと複雑な事情が絡んでくるんですね…。ご自身のアイデンティティや、ある種の『サンクコスト』、つまり今まで投じてきた時間や労力が惜しい、みたいな心理も働くのでしょうか?」
ほむほむ先生「鋭い指摘ですね。まさにその通りで、心理学で言う『信念固執』 や、これまで築き上げてきたものへの『公的コミットメント』が、変化を難しくする大きな要因といえるでしょう[9]。特に、自分の主張を支持してくれるコミュニティの中で活動していると、そこから抜け出すのは並大抵のことではないと思います。」
科学的根拠が否定されても…アンドリュー・ウェイクフィールド氏の論文問題

ChatGPTで作画
A先生「アンドリュー・ウェイクフィールド氏のケースも考えさせられますよね。MMRワクチンと自閉症を結びつけたとされる論文は、後に不正が判明して撤回され、本人は医師免許も剥奪されたと聞いています[10]。科学的には完全に否定されたにも関わらず、今なお反ワクチン運動に影響を与え続けているというのは…これはまた、ケネディ氏とは違った根深さ、難しさを感じます。一体どうしてなんでしょう?」
ほむほむ先生「そうですね。ウェイクフィールド氏の場合は、科学的な根拠が完全に崩れた後でも、一度、ある種の運動の『顔』や象徴のような存在になってしまった人物の影響力が、いかに強く残り続けるかという、典型的な例と言えるでしょう[11]。彼のように、反ワクチン活動そのものが自己のアイデンティティや活動の中心になってしまうと、過去の誤りを認めることの個人的、あるいは職業的なコストは、計り知れないほど大きくなってしまうのでしょうね。もはや後戻りできない地点をとうに過ぎてしまっているといえるでしょう。」
A先生「象徴、ですか…。一度そういうイメージが広まってしまうと、それが事実かどうかということよりも、その『物語』を信じたい人たちにとっては、修正がすごく難しいのかもしれませんね。なんだか、やるせない気持ちになります…。それに、彼を信奉する人たちにとっては、彼が間違いを認めることは、自分たちの信じてきたものが崩れることにも繋がるから、余計に受け入れがたいのかもしれませんね。」
『ほむほむ先生の医学通信』では、様々な学会で委員を務め25年以上の臨床経験を持つ小児科医が、医学知識をわかりやすく解説します。無料登録で定期的に記事をお読みいただけるほか、サポートメンバーにご登録いただくと過去の記事アーカイブすべてにアクセスできます。皆様のサポートは子どもたちの健康に関する研究継続に役立てられております。よろしければご登録をご検討ください。本記事は、登録後に全文無料で閲覧可能です。
この記事は無料で続きを読めます
- 信念を変えることの難しさ~個人的・社会的コストとは~
- 変化への道筋:個人的経験や新たな情報がもたらす可能性
- まとめ
- 参考文献
すでに登録された方はこちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績